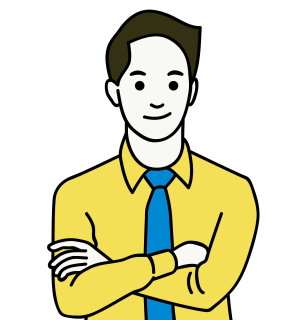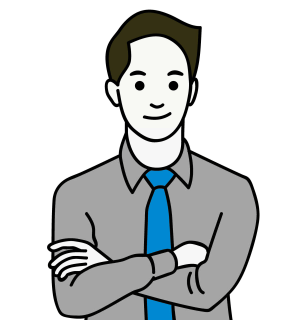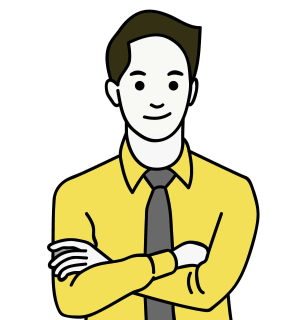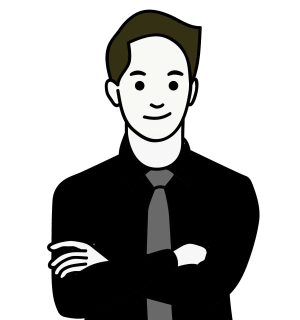はじめに
企業が従業員の住居をサポートするために活用できる「借り上げ社宅」は、福利厚生の充実や人材確保の面で大きなメリットをもたらします。ただし、契約形態や費用負担、税務上の取扱いなどには細かなルールや一般的な傾向が存在するため、事前にしっかりと確認したうえで導入することが大切です。
そこで、今回は借り上げ社宅の導入を検討している方に向けて、契約や費用、税務の基礎知識を詳しく解説します。また、実際にどのような流れで借り上げ社宅を契約し、管理していけばいいのか、一般的な運用フローについてもわかりやすくまとめました。
借り上げ社宅の円滑な導入・運用に向けて、ぜひ参考にしてください。
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、『企業側の立場にたった社宅代行』をコンセプトに、社宅管理の効率化を実現できる多彩なサポートサービスを提供しております。費用について気になる方は、ぜひ以下の料金シミュレーターをお試しください。
>>料金シミュレーターを試してみる
そもそも「借り上げ社宅制度」とは

借り上げ社宅制度とは、企業が不動産業者からマンションやアパートといった賃貸物件を法人契約で借り上げ、従業員に貸し出す福利厚生制度のことです。家賃の一部を企業が負担するスタイルで運用されるケースが多く、主に以下のような目的で導入されています。
- 福利厚生の充実
- 人材確保・採用力の強化
- 転勤・異動時の住居手配の効率化
- 節税対策
なお、企業が従業員に住居を提供する制度には「社有社宅」や「社員寮」も含まれますが、借り上げ社宅とは以下の通りに特徴が大きく異なります。
| 制度名 | 契約形態 | 特徴 |
|---|---|---|
| 借り上げ社宅 | 賃貸契約(法人) | 物件選択の自由度が高い |
| 社有社宅 | 自社所有 | 固定資産税や管理負担が発生 |
| 社員寮 | 自社所有 | 食堂や浴場といった共有スペースの運用・管理が必要 |
社有社宅や社員寮は企業が物件を保有しているため、管理コストや手間が発生します。また、従業員にとって物件選択の自由度が低いことも借り上げ社宅との明確な違いです。
社宅の概要については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅とは?寮や住宅手当との違い、メリット・デメリットまで
借り上げ社宅制度を導入するメリット
借り上げ社宅制度は、企業と従業員の双方においてさまざまなメリットがあります。それぞれの視点による主な魅力は以下の通りです。
【企業側のメリット】
・福利厚生費として損金処理を行える
従業員から「賃料相当額の50%以上」を徴収すれば、企業負担分は福利厚生費として経費計上でき、法人税の節税につながります。
・社会保険料の負担を軽減できる
借り上げ社宅は給与扱いにならないため、企業負担分の社会保険料を抑えられます。
・採用力・定着率の向上を期待できる
住宅支援制度の充実は、若手人材や地方からの採用において大きなアピールポイントとなり、離職率の低下にも寄与します。
・管理負担が少ない
民間から物件を借りる形式のため、企業が建物を所有・管理する必要がなく、固定資産税や修繕費の負担を回避できます。
【従業員側のメリット】
・費用負担を抑えられる
借り上げ社宅では企業が家賃の一部を負担するため、従業員は通常の賃貸よりも低いコストで住むことが可能です。また、敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用も企業が負担することが一般的で、従業員はまとまった資金を用意する必要がありません。
・手続きの手間がかからない
借り上げ社宅では、物件探しや賃貸借契約手続きなどを企業側が行うため、自分で賃貸物件を契約するよりも手間をかけずに住居を構えられます。
・所得税や社会保険料の負担が軽減される
従業員が賃料相当額の50%以上を支払う場合、家賃の企業負担分は福利厚生費となって給与に含まれないため、税負担が軽くなります。同様に、給与を基準に算出される社会保険料の負担も軽減されます。
※詳細は「借り上げ社宅の費用に関するルール」の見出し内で詳しくご紹介しています。
借り上げ社宅の契約に関するルール

借り上げ社宅のメリットを最大限に享受するためには、まずは契約に関する以下のルールをしっかりと確認しておくことが大切です。
契約期間と入居期限について
借り上げ社宅において、多くの企業では契約期間を2〜3年程度に設定しています。契約満了時には企業が更新の可否を決定しますが、その際には従業員の勤務状況(転勤の有無や退職予定など)や社宅の利用状況(居住実態や規程違反の有無など)によって継続利用が妥当かどうか判断するケースが一般的です。
また、借り上げ社宅の運用にあたっては「入居期限」を設ける企業が多く、これは従業員が借り上げ社宅に住むことができる最大の期間を指します。同一従業員が長期間にわたって社宅を占有することで、他の従業員が利用できなくなる事態を防ぐためのルールであり、一般的には5〜10年程度に設定している企業が多い印象です。
入居資格と対象者について
借り上げ社宅の入居資格と対象者は企業ごとに異なりますが、一般的なルールとしては、企業の人事戦略や福利厚生方針に基づいて条件が設定される傾向です。以下に、よく見られる入居資格と対象者の条件をご紹介します。
【一般的な入居資格の傾向】
- 転勤・異動を伴う従業員
- 新卒・中途採用などの新規入社者
- 自宅が勤務地から遠く、通勤時間や交通費が過度にかかる従業員
- 持ち家・投資物件を保有していない従業員
【対象者に関するよくある設定例】
- 「30歳未満」「35歳未満」といった年齢制限(若手従業員の定着支援が目的)
- 「入社3年以内」などの年次制限(一定期間で退去を促す運用)
- 「一般職限定」「管理職」といった職務内容に応じた優先枠の設定
- 「単身者限定」「扶養家族ありの世帯主限定」 (社宅の間取りや物件仕様による制限)
なお、入居資格および対象者を設定する際は、公平性や合理性、運用のしやすさを意識して整備することが大切です。
借り上げ社宅の費用に関するルール

初期費用の負担について
借り上げ社宅を導入する際にはさまざまな費用がかかり、企業と従業員のどちらが負担するのかは企業の社宅規程によって異なります。一般的な傾向は以下の通りです。
| 項目 | 概要 | 一般的な負担者 |
|---|---|---|
| 敷金 | 家賃滞納や原状回復の担保としてオーナーに預ける費用 | 企業 |
| 礼金 | 契約時にオーナーへ支払う謝礼(返金なし) | 企業 |
| 仲介手数料 | 不動産会社への報酬 | 企業 |
| 前家賃 | 入居月の家賃(通常は日割り+翌月分) | 企業 |
| 火災保険料 | 火災・水害・損害賠償などに備える保険料(2年契約が一般的) | 企業が全額または一部負担 |
| 保証料 | 家賃保証会社へ支払う費用 | 企業 |
| 引っ越し費用 | 運送会社へ支払う費用 | 企業が全額または一部負担 |
借り上げ社宅の初期費用の負担については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>借り上げ社宅の初期費用は誰が負担する?会計処理の方法を紹介
家賃の負担について
借り上げ社宅制度において、家賃の負担者に関する法的なルールはありません。そのため、企業は従業員の自己負担額と企業負担額のバランスを自由に決めることが可能で、一般的には従業員の自己負担額を「賃貸料相当額の20〜50%」の範囲内で設定しているケースが多くみられます。
ここでぜひ注目したいのが、税務上の非課税ルールです。借り上げ社宅においては以下の条件を満たす場合に企業負担分を「福利厚生費」として経費計上することが可能で、従業員側にも給与課税されない扱いになります。
【借り上げ社宅の家賃が非課税になる条件】
- 契約名義が企業(法人)であること
- 従業員から「賃貸料相当額の50%以上」を徴収していること
※賃貸料相当額とは課税額を決めるための基準となるもので、以下の3つの計算式で求めた合計額を指します。
- 1. 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
- 2. 12円 ×(建物の総床面積÷3.3㎡)
- 3. 敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
このため、節税したい場合は従業員の自己負担額を「賃貸料相当額の50%以上」に設定するとよいでしょう。
借り上げ社宅の家賃負担については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅の会社負担割合はどれくらい?節税効果を高める方法とは
共益費・光熱費の負担について
共益費と光熱費の負担についても法的なルールはなく、企業の方針で自由に決めることが可能です。ただし、一般的な傾向は存在するため、ぜひ参考にしながら決定するとよいでしょう。
まず、共益費は建物の共用部分(廊下・階段・エレベーター・ゴミ置き場など)の維持管理にかかる費用のことで、家賃の5〜10%程度が相場となっています。借り上げ社宅の場合は企業が賃貸契約者となるため、共益費も企業が支払うケースが多いですが、企業の方針によって従業員から一部または全額を徴収している場合もあります。
一方、光熱費とは居住に伴う電気・ガス・水道などの費用を指し、専有部分(居室内)の光熱費は原則として従業員の自己負担としている企業が多い印象です。
借り上げ社宅の共益費の負担については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅の共益費はどちらが負担?消費税や勘定科目についても解説
借り上げ社宅の光熱費の負担については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅の光熱費は会社負担?トラブルを防ぐ管理方法を解説
退去費用の負担について
退去費用とは入居者が退去する際にオーナーへ支払う費用のことで、壁紙や床材の張り替え、傷や汚れの修繕といった原状回復費用のほか、水回りや床、窓サッシなどの清掃を行う際のハウスクリーニング費用も含まれます。これらの費用の負担者についても法的な縛りはなく、企業の方針で自由に決めることができるため、あらかじめしっかりとルールを定めておくことが大切です。
なお、借り上げ社宅の退去費用においては故意・過失による損傷分の修繕費用は従業員負担、ハウスクリーニング費用は企業負担としているケースが多くみられます。
借り上げ社宅の退去費用については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅の退去費用は会社と入居者どちらが支払う?相場もご紹介!
借り上げ社宅の運用フローもチェック
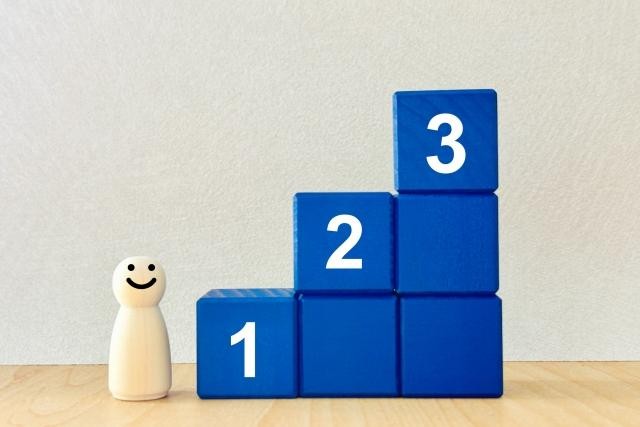
ここでは、借り上げ社宅の一般的な運用フローを解説します。スムーズな導入に向けて、ぜひチェックしておきましょう。
1. 社宅制度の設計
まずは企業の福利厚生や人材確保の観点から、社宅制度の目的を明確にします。そのうえで対象者(新入社員・転勤者など)や家賃補助の方針、運用体制、コスト試算などを検討し、制度設計の骨子を固めます。
2. 社内決議
制度設計案をもとに導入の可否を見極め、導入する場合は社内稟議や役員会での承認を得て、正式に制度導入を決定します。
3. 社宅管理規定の作成
続いて、社宅の利用条件や各種費用の負担割合、入退去ルールなどを明文化した社宅管理規定を作成します。税務リスクや公平性の観点から、規定の整備は必須です。
借り上げ社宅の契約書作成については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅使用契約書を作成するポイントと無料の雛形を公開
4. 物件選定
社宅の導入目的や社宅管理規定をもとに物件を選定します。企業が直接選定する場合もあれば、従業員が候補物件を提示する方式を採用しているケースもあります。
5. 賃貸契約手続き
物件が決まったら、企業名義で賃貸契約を締結します。トラブル防止のため、解約条件や更新料、違約金の有無なども含めた契約内容をしっかりと確認したうえで契約することが大切です。
6. 従業員の入居手続き
入居を希望する従業員に対して借り上げ社宅の運用ルールを明確に提示し、誓約書の提出などの各種手続きを進めます。
7. 定期的な管理
月次業務として家賃支払いや従業員負担分の徴収など、年次業務として契約更新の確認や支払調書の作成などの管理業務を行います。
8. 更新または退去手続き
契約更新時には家賃改定や契約条件の見直しを行い、退去時には原状回復費用・ハウスクリーニング費用の精算や敷金の返還処理などを行います。
借り上げ社宅をスムーズに運用したい方へ

前述の通り、社宅制度の導入にあたっては煩雑で専門性の高い業務が多数発生します。すべて社内で対応しようとすると担当者の負担が非常に大きくなるため、導入をためらっている企業も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、社宅の運用業務を専門業者に委託できる「社宅代行サービス」です。契約・更新・退去・家賃管理などをアウトソースすることで、入退社や異動が集中する時期でも本来の業務に集中できるほか、専門知識がなくても円滑に社宅を運用できるなどのメリットがあります。
社宅代行サービスの特徴や選び方については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅代行サービスとは?メリット・デメリットや選び方を解説
その中でLIXILリアルティの社宅代行サービスは「企業側の視点に立った社宅代行」をコンセプトに各種サービスをご提供しており、社宅業務の最大80%の代行が可能です。実際に導入された企業様からは「1か月で50件の異動という繁忙期にもしっかりと対応してくれて、物件手配のスピードと柔軟性に感謝」「全国の支店でバラバラだった社宅規定を統一でき、福利厚生の公平性が向上した」といった声が挙がっており、特に物件手配力や業務対応力、制度運用の安定性において高い評価を得ています。
導入前に費用感を把握できる料金シミュレーションもご用意しているので、社宅制度の見直しや効率化を検討している企業様はぜひチェックしてみてください。
まとめ
借り上げ社宅を運用する際には、今回ご紹介したような契約・費用・税務におけるルールや一般的な傾向についてきちんと把握しておくことが大切です。そのうえで適切な運用を行うことで、福利厚生の充実や採用力強化、節税対策など、社宅運用の目的をしっかりと果たすことができるでしょう。
ぜひ心強いパートナーとして社宅代行サービスを導入し、効率的に、そして安心感を持って社宅を運用していきましょう。