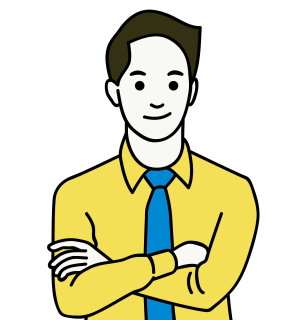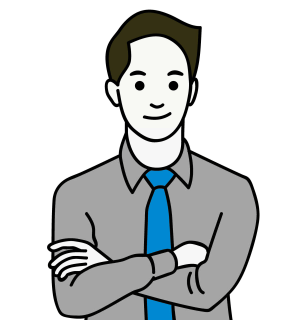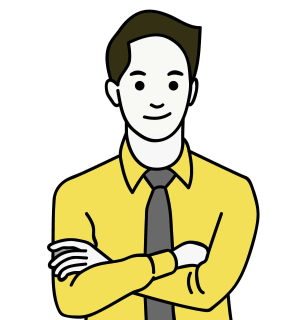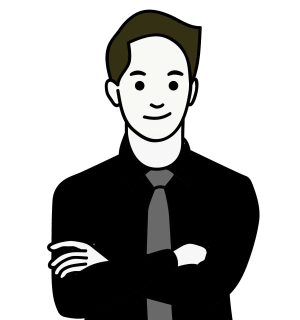はじめに
福利厚生の一環として従業員に社宅を提供する際、契約書を交わしていないと、後で「言った・言わない」でトラブルに発展する可能性があります。そのため、トラブルを未然に防ぐためにも、社宅を利用する従業員と社宅使用契約書を締結しておくことが重要です。
社内で社宅管理業務を行うことになった担当者の中には、社宅使用契約書の雛形が欲しいまたは作成したいと思っている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、社宅を提供する際に必要な社宅使用契約書の作成方法を解説します。社宅使用契約書の雛形も用意しているので、社宅使用契約書を必要としている方は是非ご利用ください。
LIXILリアルティの社宅代行サービスなら、社宅管理業務をまとめてお任せいただけます。まずは戸数を入力するだけの料金シミュレーションで、毎月の費用をご確認ください。
>>今すぐ料金をシミュレーションする
社宅使用契約書を作成する前に
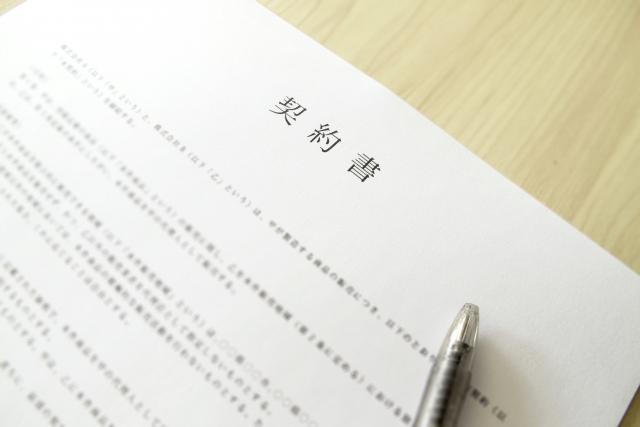
従業員に社宅を提供する際は口約束でも契約が成立します。しかし、後で「言った・言わない」でトラブルに発展する可能性があるため、トラブルを未然に防ぐためにも社宅使用契約書を締結することが重要です。
社宅管理業務を扱うことになった担当者の中には、社宅使用契約書を作成して従業員と締結すれば問題ないと考えている方もいるかもしれませんが、必要なのは社宅使用契約書の作成と締結だけありません。社宅使用契約書の作成と締結に向けた準備を行わなくてはならないため、どのような準備が必要なのか事前に確認しておく必要があります。
社宅管理規定を作っておきましょう
社宅使用契約書の作成と締結を行う前に、まず社宅管理規定を作成する必要があります。
社宅管理規定とは、会社が所有する社宅または一般的な賃貸住宅を社宅として提供する際に、入居者同士が守らなくてはならないルール、賃料や退去時における修繕費用の負担といった取り決めです。
社宅管理規定を作成していない状態では、社宅使用契約書を作成してもトラブル防止の効果が期待できない、入居者手続きをスムーズに行えない可能性があります。
従業員に社宅を提供する際のトラブルを未然に防ぐ、入居手続きをスムーズに行うためには、社宅管理規定の作成と内容を確認した従業員から誓約書にサインをもらっておくことが重要と言えるでしょう。
社宅管理規定の作り方や作成時のポイントは別記事で紹介しています。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!
社宅使用契約書に記載する内容について

社宅管理規定を作成した後は、社宅使用契約書の作成に移りますが、どのような内容を契約書に盛り込むのか分からないという方も多いと思います。社宅使用契約書に必要事項が盛り込まれていない場合は、トラブルが生じても責任の所在がどちらにあるのか判断できません。そのため、どんなトラブルに対して誰が責任を負うのかを社宅使用契約書に盛り込んでおく必要があります。
社宅使用契約書に盛り込んでおくべき内容の具体例について詳しく見ていきましょう。
内容の具体例
社宅使用契約書に盛り込んでおくべき従業員が遵守すべき事項として、以下のような事項が挙げられます。
- 社宅使用契約書の条項を遵守すること
- 給与から社宅使用料が差し引かれることに合意すること
- 社宅管理規定の内容を遵守すること
- 会社に損害を与えるような行為をとらないこと
- 他の入居者に迷惑をかけないこと
- 会社の許可を得て内装や設備を変更した場合、退去時に自己負担で原状回復すること
- 規約違反または退職・異動の場合、指定期日までに立退く、立退料を請求しないこと
火災保険は会社名義で加入するまたは個人名義で加入するケースに分けられます。個人名義で加入する場合、社員がきちんと保険に加入していなければ、火災によって生じた損害は賃借人である法人に届くため、大きな損害となります。保険に加入したかどうか不安な場合、付保証明書の提出を義務付けると安心です。
社宅使用契約書の雛形
社宅使用契約書に漏れが生じていれば、後でトラブルに発展する可能性があるため、社宅使用契約書の雛形が欲しいと思っている方も多いと思います。
以下に社宅使用契約書の雛形を用意したので、必要な部分を書き換えてご使用ください。
社宅使用契約書
株式会社○○○○以下、「甲」という)と、○○○○(以下、「乙」という)は、甲が所有する○○県○○市○○町○丁目○○番地所在の株式会社 ○○○○社宅(以下「本件社宅」という)の使用に関し、以下の通り契約する。
第1条(入居の許可)
甲は乙に対し、令和○○年○○月○○日より、本件社宅○棟○○○号室への入居を許可する。
2 乙は、善良な管理者の注意義務をもって本件社宅を使用する。
第2条(社宅使用料)
乙は甲に対し、本件社宅使用料として月額○○○○円(含む管理費)を支払う。
2 全校の支払は、毎月○○日(金融機関の休業日はその前日)までに翌月分の使用料を、乙の銀行口座より自動引き落としにて行う。
第3条(禁止事項)
乙は、社宅の使用に関し、以下の事項を行ってはならず、乙がこの禁止事項に違反した場合、甲は乙に対して本件社宅の退去を命じることができる。
①本件社宅の現状を増改築等で変更すること
②乙の家族以外の者を入居させること
③動物を飼育すること
第4条(損害の補填)
乙又は乙と同居する家族が、故意又は過失によって本件社宅を毀損、破壊するに至った場合、乙は甲に対してその損害を賠償しなければならない。
第5条(退去)
次の場合、乙又は乙の家族は、○○日以内に本件住宅を退去する。
①乙が甲を退職した場合
②乙が甲の命によって、○○県外の支店に転勤した場合
③第3条の禁止事項に反し、甲が乙に対して本件住宅の退去を命じた場合
第6条(明渡)
前条によって、乙が本件社宅を退去する際には、乙は本件社宅○棟○○○号室内のすべての動産及び本件住宅敷地内に乙の搬入した自転車等の動産を引上げ、本件社宅○棟○○○号室につき、経年的な変化を除いた入居当時の状態を回復しなければならない。
2 前条によって、乙が本件社宅を退去する場合、その当該月の社宅使用料については退去日までの日割りとする。
令和○○年○○月○○日
(甲) 住所 ○○県○○市○○町○丁目○○番地
株式会社○○○○
代表取締役○○○○ ㊞
(乙) 住所 ○○県○○市○○町○丁目○○番地
氏名○○○○ ㊞
入居から5年を経過した場合に強制退去となるケースや社宅を管理している管理人に社宅使用料を直接支払うケースなど、社宅に適用されているルールは会社ごとに異なります。
上記は社宅使用契約書の一例なので、自社のルールに合わせてしっかり作り直しましょう。
「社宅管理規定の整備が難航している」「社宅使用契約書の作成に不安がある」など、社宅運用に関するお悩みには社宅代行サービスがおすすめです。社宅管理や社宅代行サービスについてのお役立ち情報は、資料をダウンロードしてご確認ください。
>>お役立ち資料をダウンロードする
まとめ
福利厚生の一環として従業員に社宅を提供する場合、生じたトラブルの責任が誰にあるか明確にするために、社宅使用契約書を作成して社宅の利用者である従業員と締結する必要があります。
社宅使用契約書を作成して締結する前に、まず社宅管理規定を作成します。社宅管理規定とは、入居者同士が守らなくてはならないルール、賃料や退去時における修繕費用の負担といった取り決めです。
社宅管理規定と社宅使用契約書に漏れがあった場合は、それが原因でトラブルに発展する可能性があるため、トラブルを未然に防ぐためにも、どのような内容を盛り込めばいいのかよく確認してから作成しましょう。