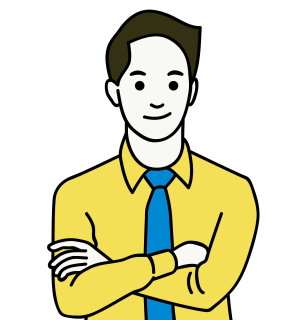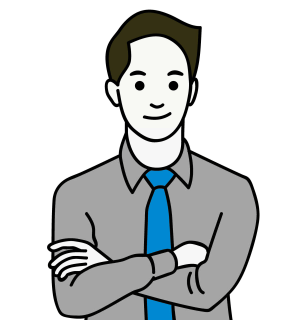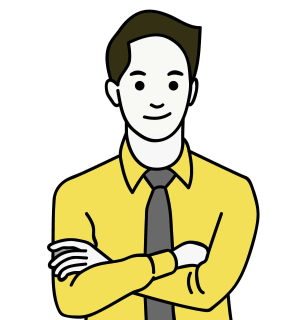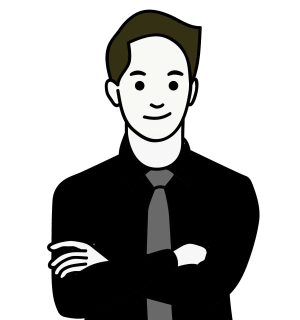はじめに
福利厚生を検討している中で、社宅制度の導入を考えている担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。社宅は、節税効果や従業員の満足度向上など、企業にとっても従業員にとっても、さまざまなメリットが期待できる制度です。
こちらの記事では、寮や住宅手当との違いや、社宅制度を取り入れた場合のメリット・デメリットを解説します。社宅制度を福利厚生として導入するか、検討するための材料としてください。
自社で新たな福利厚生を検討しているなら、満足度が高く人気のある社宅制度はいかがでしょうか。LIXILリアルティでは、社宅管理についてより知るために便利な、お役立ち資料を提供しております。ぜひご活用ください。
>>資料をダウンロードする
社宅とは

社宅とは、企業が従業員の住居を用意する福利厚生のひとつです。住居の手配から、契約にまつわる手続きまで企業側が対応するため、就職や転勤時の従業員の負担を軽減できます。従業員にとっては、比較的安価で住まいを得ることができ、満足度の高い制度のひとつです。
社宅の種類
一口に社宅と言っても、その種類は大きく2つに分けられます。それぞれの概要や特徴を押さえておきましょう。
社有社宅
社有社宅は、企業が保有する物件を従業員に貸し出す社宅のことです。保有物件は、マンションやアパート一棟丸ごとのケースと、一部屋単位のケースがあります。自社物件なので、従業員が入居・退去する場合の手続きなどがスムーズにできる点がメリットです。社宅取得時だけでなく、物件の維持・管理にも費用がかかるため、企業負担が大きいという特徴があります。
借り上げ社宅
借り上げ社宅とは、企業が物件を所有せず賃貸借契約を結んで従業員に提供する形の社宅のことです。マンションやアパートを一棟借り上げていることもあれば、一部屋単位で契約を結んでいることもあります。中には、企業が指定する物件ではなく、従業員が探してきた希望物件を契約することもあり、満足度の高い社宅制度です。物件を保有するわけではないため取得費用が不要で、物件の維持・管理にかかる負担が少ない点が企業側の大きなメリットです。一方で賃貸借契約をはじめ、さまざまな手続きを企業側が行う必要があります。
借り上げ社宅についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>借り上げ社宅はメリットがたくさん!導入のメリット・デメリット
社宅と寮の違い
社宅と寮は、法律上、明確な違いが定められているものではありません。一般的に「社宅」は、住宅のみの提供となりますが、「寮」は食事や掃除、洗濯などの生活するうえで必要なサポートが提供されるものを指す傾向にあります。そのため、社宅は家族向け、寮は単身者向けと使い分けられることも多いです。
法律で定められている違いはありませんが、どちらも福利厚生として用意するのであれば、社内規定で違いを明確に示しておくのがおすすめです。
社宅と寮の違いについては、以下の記事でも解説しています。
>>社宅と寮の違いとは?企業が導入するメリットが大きいのはどっち
社宅と住宅手当の違い
住宅に関わる福利厚生には、「住宅手当」もあります。住宅手当とは、給与に上乗せする形で家賃の補助となる費用を支払う福利厚生です。住居の形態を選ばず、賃貸でも持ち家でも平等に従業員をサポートできるメリットがあります。
ただし、住宅手当は給与と同様に課税対象になる点に注意が必要です。所得税や社会保険料も、住宅手当を含んだ金額で算出されるため、従業員も企業も負担が増えてしまいます。社宅であれば、従業員が賃貸料相当額の50%以上を負担することで、課税対象にならず、企業側も節税につながります。
借り上げ社宅と住宅手当の違いについては、以下の記事も詳しく紹介しています。
>>借り上げ社宅と住宅手当、企業が導入するならどちらがお得?
社宅制度のメリット

社宅制度には、さまざまなメリットがあります。企業側と従業員側、両方のメリットを見てみましょう。
【企業側】社宅を導入するメリット
企業側が社宅を導入するメリットは、大きく3つあります。
- 従業員の負担を軽減できる
- コスト削減・節税につながる
- 福利厚生が充実し、採用活動でアピールできる
それぞれ詳しく解説します。
従業員の負担を軽減できる
企業が物件を用意していることで、住居探しや契約手続きにかかる従業員の手間を減らせます。また、社宅になる物件は会社に近く、通勤時間の短縮にもつながり、時間的余裕が生まれるのもメリットです。
コスト削減・節税になる
社宅の場合、従業員が賃貸料相当額の50%以上を負担することで、企業が負担する社宅賃料はすべて損金計上できるため法人税の節税につながります。また、従業員から受け取る家賃分は「家賃収入」となり、企業のコスト削減にもなる点もメリットです。
福利厚生が充実し、採用活動でアピールできる
社宅制度を整備して福利厚生を充実させることで、従業員の満足度向上につながります。また、福利厚生に力を入れていると、採用活動においてもアピールでき、人材確保につなげられることも大きなメリットだと言えるでしょう。
【従業員側】社宅を利用するメリット
従業員側が社宅を利用するメリットは、3つあります。
- 家賃の負担が小さくなる
- 物件探しや手続きの手間が減る
- 住宅手当より税負担が少ない
家賃の負担が小さくなる
社宅は、通常の賃貸契約の場合で支払う家賃よりも安い賃料で住むことができることが多いため、従業員にとっては住居にかかる費用を抑えられるメリットがあります。また、本来であれば引っ越し時にかかる敷金・礼金などの初期費用や、退去する際の原状回復費用なども企業が負担してくれるケースがあり、経済的な負担が少なくなるのは嬉しいポイントです。
物件探しや手続きの手間が減る
物件探しから賃貸借契約まで対応すると時間も労力もかかります。転勤時など、急いで住居を探す必要があるときでも、社有社宅があれば社内の手続きのみで済むため、手間がかかりません。また、自分で物件を探して借り上げ社宅とする場合でも、手続き自体は企業の担当者が行ってくれるため、通常の賃貸契約よりも楽に新しい住居に住み始められます。
住宅手当より税負担が少ない
従業員が負担する社宅使用料は、一般的に給与から天引きされます。住宅手当の場合と比べると、所得が少なくなるため、所得に応じて金額が決まる、税金や社会保険料の負担も軽減されます。
社宅制度のデメリット
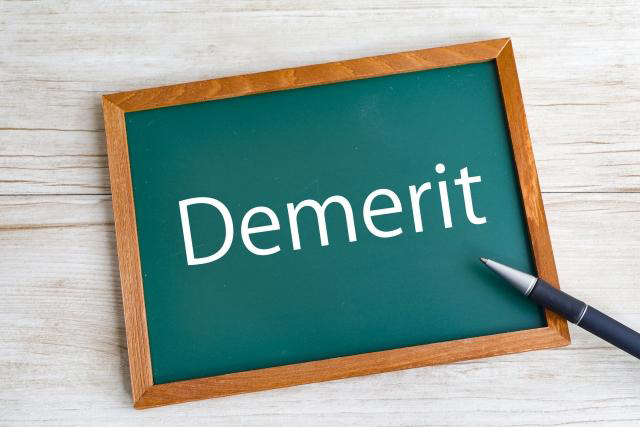
メリットの多い社宅制度ですが、デメリットもあります。企業側と従業員側、双方からのデメリットを見ていきましょう。
【企業側】社宅を導入するデメリット
企業側の社宅導入のデメリットは、以下の2つです。
- 社宅に関わるコストが発生する
- 物件を管理する手間がかかる
それぞれ、どのようなデメリットなのか確認しておきましょう。
社宅に関わるコストが発生する
社宅を運用するためには、さまざまなコストが発生します。社有社宅であれば、物件購入の費用が大きな負担となります。借り上げ社宅であれば月々の家賃のほか、入居時の初期費用、短期間で退去することになった場合の短期解約違約金、空室期間の家賃などが発生する可能性のあるコストです。
物件を管理する手間がかかる
社宅を運用していると、物件管理のための手間がかかります。社宅管理担当者をつけて、物件の管理や各種手続きに対応する必要があるためです。特に借り上げ社宅の場合は、物件ごとの手続きに加え、入居時・退去時・トラブル時には管理会社とのやり取りが発生します。異動や入社が多い時期には、短期間でたくさんの手続きが発生するため、負担が大きくなる点がデメリットです。
【従業員側】社宅を利用するデメリット
従業員にとって、社宅を利用するうえでのデメリットは、2つあります。
- 社会保障額が少なくなる
- 物件選択に制約がある
以下にて、詳しく説明します。
社会保障額が少なくなる
社宅を利用し、一定額以上の賃料を支払っていると、社会保険料も減額されます。給与を受け取る際には、一見メリットと思われますが、年金受給など社会保障を受ける際の社会保障額が減ってしまうため、デメリットにもなる点は注意が必要です。
社会保険料は、現物給与も含んだ標準報酬月額から算出されます。社宅は現物給与に該当するものですが、従業員が支払う社宅賃料の金額によって現物給与として算入されるかどうかが変わります。社会保険における取り扱いや計算方法は複雑なため、正しく理解しておくようにしましょう。
社宅と現物給与については以下の記事で詳しく解説しています。
>>現物給与とは?社会保険・労働保険における社宅の取り扱いと計算方法
物件選択に制約がある
社宅は、企業が所有する物件か、企業が賃貸借契約を結んだ物件に入居しなければならないため、必ずしも希望する物件に住めるわけではなく、物件選択に制約がある点もデメリットです。また、一棟すべてが社宅になっているケースでは、同じ企業の従業員ばかりが住んでいる状況になり、公私を分けにくくなってしまうことも考えられます。
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、全国約2,500店舗にものぼる提携不動産ネットワークで社宅物件の情報を豊富にご提供します。幅広く物件をご用意できるので、今まで物件探しに苦戦していた方にもおすすめ。「豊富な物件量」は、LIXILリアルティがお客様に選ばれる理由のひとつです。
>>LIXILリアルティの強み”豊富な物件量”についてもっと見る
社宅の家賃相場と経費にするための条件

社宅の家賃として従業員から徴収する額は、いくらが相場なのでしょうか。全額企業負担とすると経費ではなくなってしまうなど、経費とするためには条件があります。ここでは、役員社宅ではなく、従業員社宅の家賃相場と経費にするための条件について説明します。
賃貸料相当額の計算方法
社宅の家賃を経費にするためには、従業員から受け取る金額が賃貸料相当額の50%以上でなければなりません。賃貸料相当額とは、実際に支払う家賃ではなく、計算方式に則って算出する必要があります。算出方法は以下の通りです。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
賃貸料相当額の50%以上を従業員から徴収する
企業が社宅を従業員へ貸し出す場合、前述した計算式で算出した賃貸料相当額の50%以上を受け取ることで経費として計上できます。賃貸料相当額は実際の賃料よりも低くなることが多く、従業員が負担する家賃の相場は実賃料の10〜20%程度の金額になることがほとんどです。
従業員から受け取る家賃が少ない場合
一方で、従業員に支払ってもらう賃料が賃貸料相当額の50%未満の場合、賃貸料相当額と従業員から受け取っている金額の差額が給与として課税対象となります。社宅を無償提供している場合は、賃貸料相当額が全額課税対象となってしまい、従業員の負担が大きくなるため注意しましょう。ただし、医師や看護師、守衛など、職務上社宅に住む必要があるケースでは、無償貸与であっても課税対象にならないことがあります。
役員社宅の場合は、従業員社宅と賃貸料相当額の計算方法が異なります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
>>役員及び従業員に社宅などを貸した際の賃料相当額の計算方法
社宅を導入する流れ

ここからは、社宅導入の流れについて、借り上げ社宅の場合での一例をご紹介します。
社宅物件の条件を決める
社宅制度を導入するにあたり、どのような物件であれば社宅として従業員の利便性を高められるか、入居可能従業員数、初期費用や家賃、手続きなどにかかる手間も含めたコスト、住居の広さ、間取りなどの条件を決めます。
社宅物件を探す
条件に合致する物件を探します。インターネットなどを活用して、ある程度目処を立ててから、不動産会社へ相談するのが一般的です。
物件の内見をする
物件は可能な限り内見するようにしましょう。画像だけではわからなかったことや、不明点を確認することが大切です。また、周辺環境も見たうえで、住みやすさもチェックしておくのもおすすめです。
契約を締結する
物件が決まったら、契約締結へと進みます。賃貸借契約は、家賃や初期費用などの情報のほか、借主と貸主の責任範囲、契約期間、解約のルールなどが含まれるため、ひとつずつ内容を確認してから締結するようにしましょう。
従業員の入居(運用の開始)
初期費用を支払い、鍵を受け取ったら従業員に社宅制度の導入を伝えます。制度利用時のルールや注意点なども社宅管理規定とともに、書面または説明会を開催して共有するのが一般的です。従業員が入居してからは、管理会社と連携して従業員が困らないよう社宅管理を行います。
社宅制度における注意点

社宅制度を導入するときは、さまざまなことに注意が必要です。ここでは、注意しておきたいことを3つご紹介します。
社宅管理規定を作成する
社宅管理規定とは、社宅の利用ルールなどを定めたものです。入居の条件や賃料、初期費用などの取り扱いなど、細かな部分もすべてルール化しておくのがおすすめです。社宅を管理するうえで基準となるもののため、社宅導入前に策定しておきましょう。
社宅管理規定の作成でお困りなら、以下の記事がおすすめです。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!
光熱費や駐車場代は社宅の賃料には含まれない
マンションやアパートの場合に発生する共益費は家賃同様に扱えるため、企業が負担しても課税対象にはなりませんが、社宅で発生する光熱費や駐車場代は、基本的に賃料には含まれません。個人が負担すべきものですので、企業側が負担した場合は給与課税の対象になるのが通例です。
社内の運用体制を整える
社宅を運用するためには、物件管理や手続きなど、担当する人事や総務の業務負担が増加します。コストだけでなく人的リソースも必要となる点は注意が必要です。導入前に、社内で運用体制を作っておくようにしましょう。
住宅関連の福利厚生は人気!社宅制度の導入を検討中なら

社宅制度は福利厚生として根強い人気を持つ一方で、企業の社宅管理担当者にとっては運用の負担が大きくなる制度でもあります。特に、異動の多い時期や、新入社員が一気に入社するタイミング、トラブル発生時の負担は大きく、人的リソース不足に悩まれる社宅管理担当者の方も多いのではないでしょうか。
LIXILリアルティの社宅代行サービスは、柔軟なサービス対応で社宅業務を代行しています。社宅業務のコストダウンにもつながるよう経験豊富なスタッフが企業の側に立って代行するため、安心してお任せいただけるのも特徴です。
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、費用対効果の高い社宅管理サービスを提供しています。社宅代行サービスに興味がおありの方、どれくらいの費用がかかるのか気になる方は、まずは簡単なシミュレーションから始めましょう。
>>無料シミュレーションをする
まとめ
社宅とは、従業員の満足度向上につながる福利厚生のひとつで、人気の高い制度です。従業員から受け取る賃料を賃貸料相当額の50%以上に設定することで、企業と従業員双方が節税できるメリットの大きい制度となっています。
導入前には社宅管理規定などを設けたり、社宅を用意するために物件を探したりといった手間がかかり、運用にも人的リソースが必要となることがネックとなっている場合には、社宅代行サービスの利用がおすすめです。社内業務の負担をかけることなく、コストも最小限に押さえられる社宅代行サービスを活用しながら、福利厚生を充実させてみませんか。