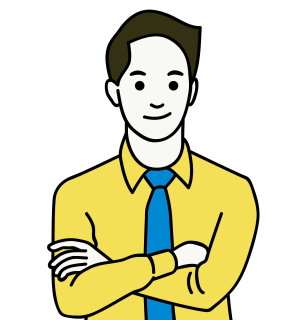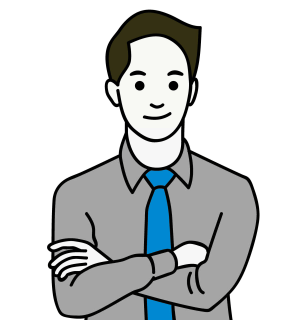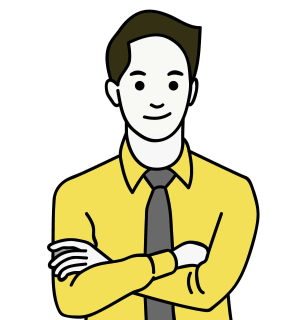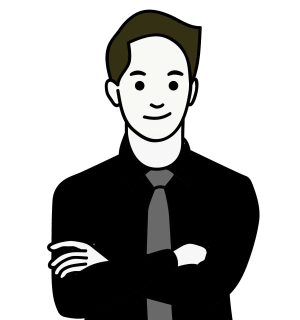はじめに
住宅系の福利厚生を検討している企業の担当者の中には、借り上げ社宅と住宅手当のどちらを導入すべきか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
両者にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらが自社に合っているのかよく理解してから導入することが大切です。
この記事では、借り上げ社宅と住宅手当の違いや両者のメリット・デメリット、導入の流れなどについて解説します。
LIXILリアルティでは借り上げ社宅導入のご支援から、社宅管理業務に関わるご相談を承っております。社宅に関するお悩みをお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
>>借り上げ社宅について相談する
借り上げ社宅と住宅手当の違い
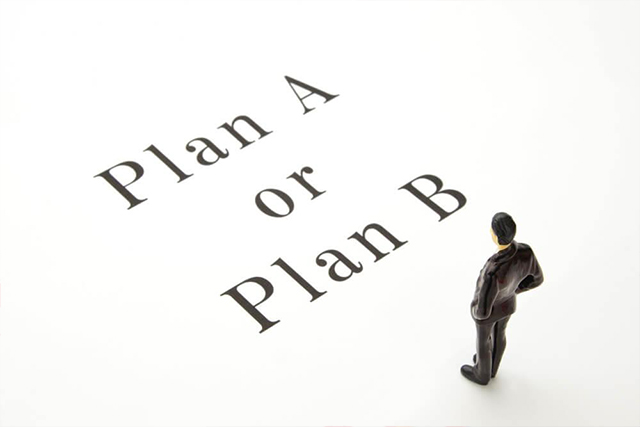
福利厚生とは、企業が従業員やその家族に提供する給料や賞与以外の報酬・サービスのことです。福利厚生を充実させれば、従業員の満足度が上昇する、新規雇用を確保しやすくなる、退職を防ぐなどの効果を期待できます。
例えば、社員食堂を設置する、育児手当や資格取得手当などを支給する、スポーツクラブを利用できるなどの福利厚生が挙げられます。
住宅系の福利厚生は、借り上げ社宅と住宅手当の2種類です。借り上げ社宅と住宅手当の違いについて、以降で詳しく見ていきましょう。
借り上げ社宅とは
借り上げ社宅とは、会社が従業員のために用意した住居のことです。
例えば、賃貸住宅を会社が家賃5万円で借りて、従業員が給与から社宅使用料として2万5,000円を支払って借りるといったかたちです。
賃貸物件の家賃は、契約者である会社が一旦全額支払います。家賃の負担割合は各会社で異なりますが、会社が定めている負担割合に従って、家賃の一部が給与から天引きされるのが借り上げ社宅の特徴です。
従業員が支払う社宅利用料の割合によっては、所得税や社会保険料にかかる金額を少なくすることができるため、従業員・企業ともに負担を小さくできます。
住宅手当とは
住宅手当とは、従業員の住居費の負担を軽減する目的で、会社が給与に上乗せする報酬のことです。
例えば、賃貸住宅を従業員が家賃5万円で借りて、会社から住宅手当として2万5,000円を受け取るといったかたちです。
賃貸物件の家賃は、契約者である従業員が一旦全額支払います。住宅手当の支給額は会社ごとに異なりますが、家賃の支払いに充てることによって住居費用の負担を軽減できるという点は、社宅と同じです。
従業員本人が物件探しから契約までを行うため、自由に物件を選べることや、企業の管理コストが小さいことが特徴です。
【まとめ】借り上げ社宅と住宅手当の違い
借り上げ社宅と住宅手当の違いをまとめると、以下の通りです。
| 借り上げ社宅 | 住宅手当 | |
|---|---|---|
| 賃貸借契約の契約者 | 会社 | 従業員 |
| 家賃を支払う人 | 会社 | 従業員 |
| 福利厚生の仕組み | 会社が家賃の一部を支払う | 従業員に家賃補助を現金で支給 |
| 物件の選択 | 制限される場合がある | 自由に選べる |
| 企業の管理負担 | 管理コストが増える | 一般的に少ない |
| 節税効果 | 大きい | 小さい |
借り上げ社宅では、従業員にかわって会社が物件の賃貸借契約を取りかわし、従業員から天引きした家賃も合わせて貸主に支払います。従業員は契約手続きや家賃の支払いに関わるわずらわしさがなくなりますが、自分の気に入った物件を選ぶことができない場合があります。企業からみると、支払った家賃を経費計上することで節税効果を得られますが、社宅を管理する体制を整える必要があります。
一方、住宅手当の場合は、会社からのサポートは給与に上乗せされた金銭のみであるため、従業員が自ら物件を探し、契約をしなければなりません。従業員は自分の好きな物件を選ぶことができますが、給与所得の増加とともに、所得税や住民税、社会保険料などの負担も大きくなります。
同じ住宅に関連する福利厚生ではありますが、両者のメリット・デメリットは大きく違います。昨今は両者の特徴やメリット・デメリットを踏まえて、企業・従業員ともに節税効果が期待できる借り上げ社宅を導入する企業が増えています。
借り上げ社宅のメリット・デメリット

借り上げ社宅と住宅手当のどちらが合っているかは、会社によって異なります。自社に合った福利厚生制度を導入するためにも、両者のメリット・デメリットを把握しておくことが大切です。
まずは、借り上げ社宅のメリット・デメリットについて、詳しく解説していきます。
借り上げ社宅のメリット
借り上げ社宅のメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 節税効果がある
- 住宅手当と比べて従業員の税負担が小さい
- 従業員の満足度向上や採用活動のアピールポイントになる
節税効果がある
会社が負担する家賃は、福利厚生費として経費に計上できます。法人税は、利益から経費を含む損金の金額を除いた所得に対して課税されるため、節税に効果的です。
また、敷金や礼金、前払い家賃、更新料、引越し費用といった社宅提供時に発生する費用も、福利厚生費として経費計上できます。
例えば、仮に40歳未満の年収500万円の方が月5万円の家賃補助を受けるケースと月5万円の家賃負担で社宅を利用するケースの節税効果を比較します。
家賃補助は所得に上乗せされるため、実質的な所得は560万円です。社宅の場合、引かれる家賃は税金や社会保険料の計算上、影響はないためそのままです。所得税と住民税を比較すると以下の通りです。
| 家賃補助 | 社宅 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 178,900円 | 140,600円 |
| 住民税 | 282,800円 | 245,300円 |
| 合計 | 461,700円 | 385,900円 |
社宅のほうが76,700円も所得税・住民税の負担を軽減できています。
法人の実質的な家賃負担額が月10万円だった場合、120万円経費が増えることになるため、法人税の負担を最大278,400円抑えることが可能です。
この一定額以上の家賃負担のことを、賃料相当額といいます。
賃料相当額について詳しく知りたい人は、以下の社宅家賃の計算についての記事をご覧ください。
>>役員及び従業員に社宅などを貸した際の賃料相当額の計算方法
住宅手当と比べて従業員の税負担が小さい
住宅手当の場合は、会社が従業員に支払う住宅手当は給与として扱われます。課税対象となる従業員の所得が増えるため、従業員は所得税と住民税の負担が大きくなるほか、会社と従業員で折半している社会保険料の負担も大きくなります。
しかし、借り上げ社宅の場合には、従業員が負担する家賃は給与から天引きされることで所得が減ります。そのため、従業員は所得税や住民税の負担を軽減することができ、会社と従業員ともに社会保険料の負担も減らすことができます。
以下の条件で従業員の手元に残るお金がどのくらい変化するか見てみましょう。
- 基本給15万円の独身社員
- 家賃7万円の物件に住む従業員に4万円の住宅手当を支給(住宅手当)
- 家賃7万円の物件で会社が4万円負担、従業員は3万円負担(借り上げ社宅)
住宅手当の場合は、基本給15万円に4万円の住宅手当が上乗せされるので給与所得は19万円となります。社会保険料や所得税などを引かれ、家賃7万円を支払うと手元に残るのは88,000円程度です。
借り上げ社宅の場合は、住宅手当のような上乗せがないため、給与所得は15万円のままです。給与所得が変わらないため、住宅手当のように社会保険料や所得税の金額が増えることなく、家賃(社宅利用料)の3万円を引いても手元に残るのは95,000円程度と、7,000円多くなります。
手取りを減らさずに住居費の負担を軽減できる点が、借り上げ社宅の大きなメリットです。
従業員の満足度向上や採用活動のアピールポイントになる
住宅関連の福利厚生は、大きくなりやすい住居費の負担を抑えられるため人気です。また、従業員の満足度向上につながるだけでなく、福利厚生に力を入れている企業として採用活動時のアピールポイントにも活用できます。
少子化による人口減少により人材確保が困難になりつつあるなか、借り上げ社宅の導入は、離職防止や優秀な人材の確保に有用です。
借り上げ社宅のデメリット
借り上げ社宅のデメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 社宅管理業務が煩雑
- 空き物件の家賃や違約金が発生する可能性がある
社宅管理業務が煩雑
住宅手当の場合は、会社ではなく従業員が契約者となります。そのため、賃貸契約に関連する業務は基本的に従業員がすべて行うため、会社側の負担はほとんどありません。
しかし、借り上げ社宅の場合は、社宅の管理を会社が行わなくてはなりません。例えば、借り上げ社宅に住む従業員の入居や退去の手続き、社宅の保険加入、大家さんへの支払い、税務署に提出する資料作成などです。
社宅管理業務は従業員の入れ替わりの生じやすい4月や9月に集中するため、社内に専門部署を設けることは少なく、他の部署がその時期だけ兼任することが多い傾向です。
その結果、負担が大きくなることによって、多忙が原因による人的ミスが発生しやすくなるなど、従業員の不満が募ります。
そこで、上記のような問題を解決する方法としておすすめなのが、社宅代行サービスの利用です。社宅代行サービスは煩雑な社宅管理業務を代行してくれるので、社宅管理業務の負担を軽減できます。
空き物件の家賃や違約金が発生する可能性がある
住宅手当では、賃貸契約の契約者は従業員です。そのため、解約によって違約金が発生した場合は、従業員が負担することになります。
しかし、借り上げ社宅では、契約者が会社です。転勤などの理由で契約を途中解約することになった場合、基本的には会社が違約金を負担しなくてはなりません。
また、長期契約の借り上げ社宅においては、借り上げ社宅に入居者がいない場合でも、空家賃が発生する点に注意してください。
借り上げ社宅のメリット・デメリットについては以下の記事でも解説しています。
>>借り上げ社宅はメリットがたくさん!導入のメリット・デメリット
住宅手当のメリット・デメリット

最近は、住宅手当よりも借り上げ社宅を選択する企業が増えています。しかし、会社によっては住宅手当を選んだ方が良いケースもあります。
ここからは、住宅手当のメリット・デメリットを詳しく説明していきます。
住宅手当のメリット
住宅手当のメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 比較的導入しやすい
- 運用の負担が軽い
- 従業員が住みたい物件を選べる
比較的導入しやすい
借り上げ社宅の場合、家賃負担額をいくらにするのかといった導入計画の立案、社宅規定の作成、運営方法の検討など、導入までに時間と手間がかかります。
一方、住宅手当の場合、支給条件と支給金額を決定するだけで、導入できます。導入までの時間と手間を大幅に軽減できるほか、スムーズに導入できる点は、大きなメリットです。
運用の負担が軽い
借り上げ社宅は、導入時に時間と手間がかかるだけでなく、社宅に住む従業員の入居や退去の手続き、社宅の保険加入、大家さんへの支払い、税務署に提出する資料作成など、導入後の運用負担も大きいです。
一方、住宅手当の場合、基本的に住宅手当を毎月の給与に上乗せして払うだけです。そのため、借り上げ社宅よりも運用の負担を軽減できます。
従業員が住みたい物件を選べる
借り上げ社宅の場合は、契約できる物件がすでに決められていたり、物件の条件が規定で定められていたりと、物件選択が制限されてしまうことがあります。しかし、住宅手当の場合は、そのような制限なく、自分が好きな物件を契約できます。
ペット可の物件に住みたい、一人暮らしではあるものの広めの部屋に住みたいといった条件を希望する従業員も一定数います。そのような従業員にとっては、住宅手当のほうが使いやすい制度となる場合が多いです。
住宅手当のデメリット
住宅手当のデメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 課税対象になる
- 支給条件の設定が煩雑
課税対象になる
住宅手当の場合、住宅手当を給与に上乗せして支払うことによって従業員の所得が増えるため、法人税や社会保険料の負担が大きくなります。
借り上げ社宅の場合でも、住宅・物件の現物給付にあたるため、通常は所得税や社会保険料の算定対象となりますが、従業員が一定額以上の社宅利用料を会社に支払うことで、所得税や社会保険料の対象に含まれなくなります。
従業員の雇用を安定させる目的で福利厚生を充実させようとしても、費用負担や税負担の増加で会社の経営が悪化しては意味がありません。
支給条件の設定が煩雑
借り上げ社宅の場合、社宅利用を希望する人にターゲットが絞られるので、支給条件の設定はそこまで煩雑ではありません。
しかし、住宅手当の場合、ターゲットを絞るのが容易ではありません。例えば、従業員全員に一律支給だと、実家暮らしの人は住居費の負担がなくても給与が増えることになるので、公平とは言えません。
また、住居費は地域差も大きく、一律で支給した場合は住居費負担の大きい地域に住む従業員の不満が募る可能性もあります。このように、支給条件の設定が難しいという点も、デメリットとなります。
借り上げ社宅や住宅手当などの福利厚生導入の流れ
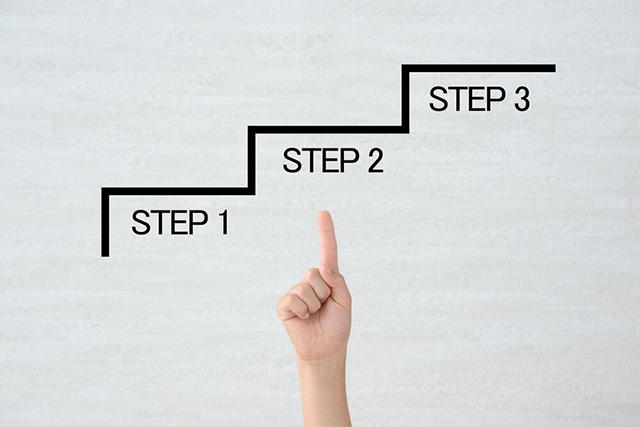
福利厚生を導入したものの、期待した効果が得られなかった、会社の負担が大きいなどの理由で廃止を検討する企業も少なくありません。しかし、これらは簡単に廃止できるものではないので注意が必要です。福利厚生制度は労働条件に関連するため、廃止は不利益変更にあたります。一度導入すると、廃止には従業員の合意を必要とするような手続きを踏む必要があるのです。
そのため、福利厚生制度を導入する際は、本当に導入すべきかどうか、適切な流れを把握した上で、制度を導入することをおすすめします。
福利厚生制度を導入する際の基本的な流れは、以下の通りです。
- 導入目的の明確化
- 導入計画の立案
- 社内規定の作成
- 運営方針を固める
- 従業員への説明と同意の取り付け
- 必要書類を準備する
それぞれの流れについて、詳しく見ていきましょう。
導入目的の明確化
まずは、どのような目的で福利厚生制度を導入しようとしているのかを明確にします。
福利厚生制度は、従業員の雇用環境を充実させることで雇用の安定を図ることを目的とすることが多いですが、目的が曖昧な場合は、従業員のニーズに合っていない制度を導入する恐れがあります。その結果、従業員が利用しなかったり、導入コストだけが発生したりといった事態になりかねません。
導入目的を明確にすることから取り組むことが大切です。
導入計画の立案
導入目的を明確にした後は、導入に向けた予算やスケジュールなどの計画を立案します。
住宅手当の場合は支給条件や支給額、借り上げ社宅の場合は会社負担額をいくらに設定するか、などです。
住宅手当の場合は開始時期を気にする必要はありませんが、借り上げ社宅の場合は従業員の入れ替わりが多い4月には間に合わせる必要があります。逆算して、無理のない計画を立案するのがポイントです。
社内規定の作成
利用条件は何なのか、金額はいくらなのかなど、労使間で誤解が生じないよう、導入計画に基づいて福利厚生規定(社内規定)を作成する必要があります。
福利厚生制度をスムーズに運用したり、トラブルを回避したりするためには、社内規定以外に担当部署や経理部署向けのマニュアルも作成しておくこともおすすめです。
社宅管理規定の詳細や作成方法について詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!
運営方針を固める
福利厚生制度を導入する場合には、福利厚生業務を社内で担当することになります。業務は多岐に渡るため、どのような業務を行うのか、誰が担当するのかを明確にしておく必要があります。
借り上げ社宅は住宅手当と比べて担当者の業務負担が大きいため、社宅代行サービスといった外部委託を検討するのも選択肢の1つです。
社宅管理業務にかかる費用や従業員の負担などを総合的に判断しながら、決めていきましょう。
従業員への説明と同意の取り付け
福利厚生制度を導入しても、従業員が利用してくれなければ意味がありません。そのため、どのような目的で制度を導入しようとしているのか、どのような内容なのかを従業員に説明して周知させる必要があります。
また、福利厚生制度の導入は労働条件や就業規則の改定に当たるため、後でトラブルに発展することを未然に防ぐためにも、従業員の同意を必ず取り付けておくことが大切です。
必要書類を準備する
住宅手当を導入する際は入居契約書(賃貸借契約書)、借り上げ社宅を導入する際には社宅利用申請書などの書類を用意しなくてはなりません。
スムーズに運営するためにも、何が必要なのかを事前に確認して、準備しておきましょう。
借り上げ社宅導入をご検討中の企業様はご相談ください

住宅系の福利厚生を充実させたいと考えている場合には、節税効果が期待でき、昨今導入企業が増えている借り上げ社宅の導入をおすすめします。しかし、借り上げ社宅の場合は、煩雑な社宅管理業務を行わなくてはなりません。
LIXILリアルティの社宅代行サービスであれば、社宅管理業務を一元化でき、高い業務品質を享受することによって煩雑な社宅管理業務を80%削減できます。
また、高品質で豊富なサービスをリーズナブルに提供しているので、社宅管理業務のコストダウンを図ることも可能です。
社宅管理業務の負担を軽減したい、コストダウンを図りたいと考えている担当者の方は、一度ご相談ください。
まとめ
福利厚生制度を導入し、従業員の雇用環境が良くすることで、雇用の安定を図ることが期待できます。
福利厚生制度には、社員食堂の設置、育児手当や資格取得手当などの支給、スポーツクラブの利用など、さまざまな種類がありますが、なかでも住宅系の福利厚生制度を導入する企業が多く見られます。
住宅系の福利厚生には借り上げ社宅や住宅手当などがあります。自社に合った方法を選ぶため、両者の特徴をしっかりと把握することが大切です。
昨今は、借り上げ社宅を導入する企業が増えていますが、借り上げ社宅の場合には煩雑な社宅管理業務を社内で取り組まなくてはなりません。社宅管理業務は外部に委託することも可能なので、業務負担を軽減したい、コストを軽減したいという人は、社宅代行サービスの導入を検討するのをおすすめします。