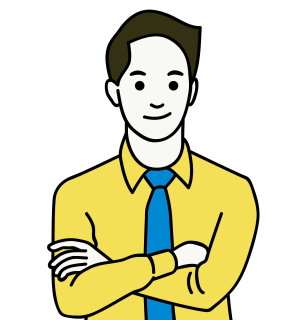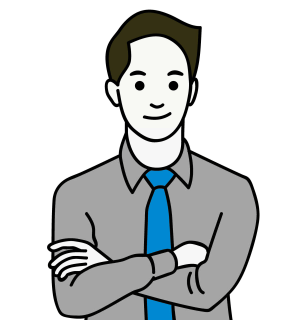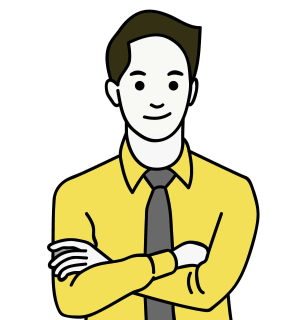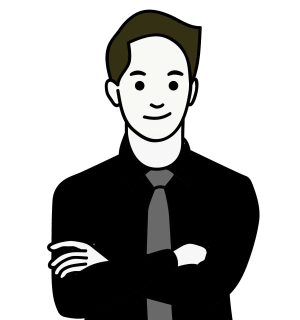はじめに
福利厚生を充実させる目的で社宅を導入すべきかどうか悩んでいる方も多いと思います。社宅を導入すれば、福利厚生が充実するので良い人材が集まりやすくなる一方、会社の費用負担が大きくなります。
社宅を導入することにはメリットだけでなくデメリットも伴うため、社宅を導入してから後悔しないためにもメリットとデメリットを把握してから導入することが重要です。
この記事では、社宅の導入を検討している方に向けて、社宅とは何なのか、会社に社宅を導入するメリットとデメリットを分かりやすく解説します。社宅の導入を検討している方は、是非参考にしてください。
社宅管理のノウハウや、社宅代行サービスについてさらに知りたい方に向けたお役立ち資料を無料でダウンロードできます。検討を進める材料として、ぜひご活用ください。
>>資料を無料ダウンロードする
社宅とは

求人広告を見てみると、福利厚生の欄に「社宅」と記載されている会社がありますが、社宅とはどんな住居を意味するのでしょうか?
社宅とはどのような住居を意味するのか、おすすめの社宅の提供形態を詳しく見ていきましょう。
企業が社員へ貸し出す住居
社宅とは、会社が自社の従業員に貸し出す住居です。社宅として提供される住居に制限はなく、マンションやアパートなどの集合住宅以外に、一戸建てのような戸建住宅が提供されるケースもあります。
社宅が用意されているからと言って、従業員は必ず社宅に住まなければならないというわけではありません。社宅への入居は強制ではなく、希望者のみが入居する仕組みになっています。
社宅には、会社が所有している物件を従業員に提供する社有社宅と、会社が物件を借り上げて従業員に提供する借り上げ社宅の2種類があります。最近は借り上げ社宅を導入する会社が増えましたが、なぜ借り上げ社宅を導入する企業が増えているのでしょうか?
これから社宅を導入される企業は「借り上げ社宅」がおすすめ
これから社宅の導入を考えている方には、社有社宅よりも借り上げ社宅がおすすめです。社有社宅は、物件を取得する際に初期投資が必要になり、維持管理は基本的に会社で行うので手間がかかります。一方、借り上げ社宅は物件を所有せず、社宅の維持管理は不動産会社に委託することで初期投資や維持管理にかかる手間を軽減できます。
また、借り上げ社宅は立地や間取りを複数の物件から選べるというメリットがあります。社有社宅は居住者が従業員に限られてしまい、プライベートも従業員と顔を合わせることになって気が休まりません。そのため、従業員は社有社宅よりも立地や間取りを複数の候補から選べる借り上げ社宅を好む傾向があります。
社有社宅の場合は、会社は減損会計が導入されたことで、資産価値の下がった社宅の会計処理を行わなくてはなりません。資産価値が下がると、減価償却できる金額の下落に合わせて税法上のメリットも小さくなるので注意が必要です。
借り上げ社宅であれば上記のような税法上のリスクを気にせずに済むため、従業員だけでなく会社にとってもメリットの大きな社宅の提供方法と言えるでしょう。
借り上げ社宅と社有社宅の違い

これから社宅を導入する場合は借り上げ社宅がおすすめと言いましたが、借り上げ社宅と社有社宅にはどんな違いがあるのでしょうか?借り上げ社宅と社有社宅の違いを詳しく見ていきましょう。
借り上げ社宅とは
借り上げ社宅とは、物件オーナーや不動産会社などから賃貸住宅を借りて従業員に貸し出す社宅のことです。会社がいつでもスムーズに従業員に社宅を提供できるように常に賃貸住宅を借り上げておいて、必要に応じて従業員に提供します。
借り上げ住宅は立地や間取りを複数の候補から選べ、仕事とプライベートが混在しやすい社有社宅と比べてプライベートを充実させられるため、従業員満足度の高い福利厚生として人気です。
会社にとっては、社有社宅のように社宅を所有しないので固定資産税や都市計画税などの支出、維持や管理の手間と費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、社宅の希望者が少ない場合は、借り上げておく費用だけがかかるため、無駄な支出が増えるといったデメリットを伴うという点に注意が必要です。
社有社宅とは
社有社宅とは、会社が賃貸住宅を購入して従業員に貸し出す社宅のことです。従業員から家賃を徴収するかは会社が自由に決めることができます。
不動産という資産が手に入るため、不動産バブルの頃は社有社宅を選択する企業も数多くありました。しかし、バブル崩壊後は不動産価格が下がっており、社有社宅を選択する会社は減っています。固定資産税や都市計画税がかかる、維持や管理に手間と費用がかかるなどのデメリットもあるため、社有社宅から借り上げ社宅に切り替える会社が徐々に増えています。
住宅手当との違い
住居に関連する福利厚生は社宅だけではありません。住居を提供する社宅とは異なり、住宅手当として現金を支給する会社もあります。
借り上げ社宅の契約者は会社なので、契約や家賃の支払いなどのやりとりは会社が行わなくてはなりません。そのため、総務部や人事部などの担当部署の手間が増えるというデメリットが挙げられます。
福利厚生として住宅手当を選んだ場合、契約や家賃の支払いなどのやりとりは従業員が行うため、担当部署の手間を減らせます。また、借り上げ社宅よりも選択できる物件の立地や間取りが増える、住宅手当が所得額に上乗せされて社会保障が充実するなど、従業員満足度が高いことが大きなメリットです。
しかし、会社は住宅手当を支給すると社会保険料が増える、従業員はそれに加え所得税が増えるなど、会社・従業員ともに負担が増えるので注意しましょう。
住宅手当と借り上げ社宅の違いについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
>>借り上げ社宅と住宅手当、企業が導入するならどちらがお得?
借り上げ社宅制度を導入する5つのメリット

会社が社宅をこれから導入するのであれば借り上げ社宅がおすすめですが、導入してから後悔しないためにも借り上げ社宅のメリットとデメリットの両方を事前に把握することが重要です。借り上げ社宅のメリットには以下の5つが挙げられます。
- 社会保険料の軽減につながる
- 社員満足度が向上する
- 福利厚生が充実するため、求人でアピールできる
- 転勤者の負担が軽減され、転勤希望や快諾が増える
- 借り上げ社宅なら管理負担も少ない
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
メリット1 社会保険料の軽減につながる
住居に関連する福利厚生として住宅手当を支給した場合、給与の増加と見なされるため、社会保険料が増加します。そのため、会社の費用負担が大きくなります。
借り上げ社宅を選んだ場合、給与の増加と見なされないため、社会保険料は増加しません。そのため、住居に関連する福利厚生を検討している場合は、住宅手当の支給よりも借り上げ社宅を選んだ方が費用負担を抑えられます。
また、借り上げ社宅を導入する際は、従業員と会社の賃料の負担割合を決める必要がありますが、会社負担の賃料は経費に計上できます。会社の負担割合を増やせば、従業員満足度の上昇によって良い社員が集まる、離職率が低くなる、会社の利益を減らすことによって経費軽減が得られるでしょう。
メリット2 社員満足度が向上する
昔は一度就職した会社に長く勤務しているのが一般的でしたが、現在は転職を行う人の数が増えているため、離職者をいかに減らすかが企業の課題となっています。そこで、従業員満足度を向上させることで、離職率を低くしようと取り組む企業も増えています。
福利厚生として住居手当を支給すれば住居にかかる費用を抑えられるため、従業員満足度が高くなりますが、従業員の税負担や社会保険料の負担が増えてしまいます。しかし、借り上げ社宅であれば税負担や社会保険料の負担を増やさずに住居にかかる費用を抑えられるため、従業員満足度をさらに向上させられるでしょう。
メリット3 福利厚生が充実するため、求人でアピールできる
会社は絶対に福利厚生を導入しなければならないというわけではありません。しかし、就職活動を行っている人の中には、就職する会社を決める際の基準に福利厚生の手厚さを基準にしている人もいるため、福利厚生が充実している会社の方が良い社員が集まりやすいと言えます。
少子化による人口減少によって従業員の確保が困難になっている現状を考えると、他の会社よりも採用活動を有利に進めるには、借り上げ社宅を導入して福利厚生を充実させるのも選択肢の1つと言えるでしょう。
メリット4 転勤者の負担が軽減され、転勤希望や快諾が増える
会社の中には、拠点が複数あって頻繁に転勤が生じる会社もあります。そのような会社では、従業員は転勤を告げられるたびに新居を探さなくてはなりません。新居探しは時間と手間がかかるだけでなく、新たに敷金と礼金を支払うことになるので費用負担も生じます。
借り上げ社宅であれば、従業員は転勤が生じても新居探しがスムーズに進みます。また、新たに敷金や礼金を支払わずに済むため、転勤者の負担を軽減することが可能です。
転勤は従業員の負担が大きいので快諾されないケースも多いですが、借り上げ社宅を導入すれば転勤希望者や快諾が増える可能性が高まるでしょう。
メリット5 借り上げ社宅なら管理負担も少ない
借り上げ社宅ではなく社有社宅を選んだ場合は、不動産という資産が手に入る一方、社宅の維持管理や修繕は会社が行わなくてはなりません。そのため、社有社宅では維持管理費や修繕費などの支出が増えます。支出を減らすために、物件や設備の耐用年数を無視して修繕を行わなかった場合は、資産価値が下がるだけでなく、従業員満足度も下がるので注意が必要です。
借り上げ住宅を選んだ場合は、維持管理費や修繕費などは物件オーナーの負担になるので、会社は負担せずに済みます。社有社宅と比較して管理負担を大幅に減らせるのが借り上げ社宅のメリットと言えるでしょう。
LIXILリアルティなら、「社宅に関わる手続きや管理をまとめて任せたい!」そんなご要望にもお応えします。まずは料金シミュレーションで費用感をチェックしましょう。
>>料金をシミュレーションしてみる
借り上げ社宅制度を導入する3つのデメリット
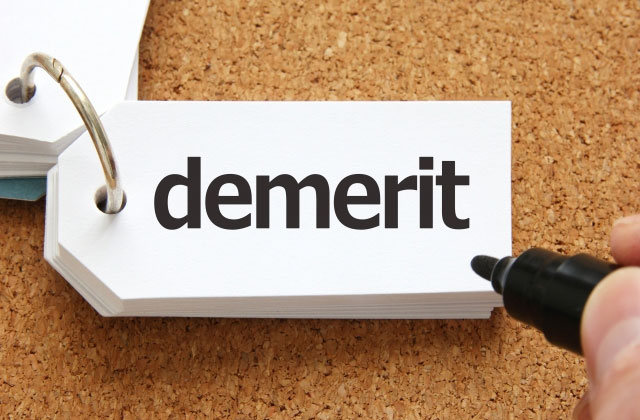
借り上げ社宅制度のデメリットには以下の3つが挙げられます。
- 契約や支払手続きの手間が発生する
- 部屋が空室になっても家賃が発生する
- 解約時に違約金が発生するリスクがある
それぞれのデメリットを詳しく見ていきましょう。
デメリット1 契約や支払手続きの手間が発生する
借り上げ社宅は会社が物件オーナーから賃貸物件を借り上げるため、契約や支払手続きは会社が行わなくてはなりません。これらの契約や支払手続きを専門的に行う部署があれば問題ありませんが、基本的には総務部や人事部などが兼任しているケースが多いため、繁忙期には従業員の負担が大きくなります。
従業員の負担が大きくなると不満が大きくなって離職率が高まる、残業代によるコスト増加が考えられるので注意が必要です。社宅の代行業者に委託すれば契約や支払手続きの手間を軽減できますが、今度は委託費用が発生します。これらの手間とどのように向き合うかが課題と言えるでしょう。
デメリット2 部屋が空室になっても家賃が発生する
借り上げ社宅は、従業員が社宅を必要な時だけ借り上げるという方法もありますが、賃貸需要の高まる時期はほとんど物件がない可能性があるので注意が必要です。そのため、借り上げ社宅が不要になったからと言って解約せずに、契約を残したままいざという時にすぐに貸し出せるようにしている会社もあります。
従業員が家賃の一部を負担する形式を採用している場合には、従業員が社宅を使用している間は家賃の一部を従業員が補ってくれますが、空室の場合全額会社負担になります。空室が多いと会社の費用負担が大きくなるので注意しましょう。
デメリット3 解約時に違約金が発生するリスクがある
社有社宅は自己所有の物件なので、解約時に違約金が発生しません。しかし、借り上げ社宅は物件オーナーと契約を交わすため、契約期間の満了前に解約した場合には違約金が発生する可能性があります。
社宅が不要になっても契約を続けている場合は違約金が発生しません。必要な時のみ借り上げるという方法を選択している場合は手軽さが魅力である一方で、途中解約になった場合は違約金が発生するリスクを伴うので注意しましょう。
短期解約違約金については、こちらの記事でも解説しています。
>>借り上げ社宅の短期解約違約金は誰が負担する?トラブルを防ぐための社宅管理規定を作るポイント
従業員が借り上げ社宅を利用するメリット

会社には借り上げ社宅を導入することにメリットがありましたが、従業員には借り上げ社宅を利用することにメリットがあるのでしょうか?従業員が借り上げ社宅を利用するメリットには以下の5つが挙げられます。
- 入社や転職時に住宅を探す必要がない
- 賃貸契約や家賃支払い手続きも不要になる
- 会社が家賃の一部負担をしてくれる
- 賃貸契約の更新料などが発生しないケースがある
- 住宅手当に比べ従業員の負担が増えない
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
メリット1 入社や転勤時に住宅を探す必要がない
会社が現在の住まいから近い場合には、入社時に新居を探す必要はありませんが、離れている場合や転勤時には新居を探さなくてはなりません。
新居を探す際は立地や家賃などにこだわりながら探すので手間と時間がかかります。しかし、借り上げ社宅が用意されている場合は新居を探す手間と時間を省けるのがメリットと言えるでしょう。
メリット2 賃貸契約や家賃支払いの手続きも不要になる
自分で新居を見つけて契約する場合は賃貸契約や家賃支払いの手続きなどを自分で行わなくてはなりません。しかし、借り上げ社宅の場合はこれらを全て会社が行ってくれるため、従業員は契約や手続きにかかる手間を省くことができます。
そのため、仕事が終わった後や休みの日に不動産会社を訪れて契約を交わす、家賃支払いの手続きを行わずに済むのがメリットと言えるでしょう。
メリット3 会社が家賃の一部負担をしてくれる
社宅に住むことの一番のメリットは、何と言っても家賃の安さです。
企業が福利厚生の一環として家賃の一部を負担してくれるので、同じ地域の家賃相場と比較しても格段に安く住むことができるため、大きな節約につながります。
メリット4 賃貸契約の更新料などが発生しないケースがある
自分で賃貸物件を探して賃貸契約を締結する場合は2年に1回の頻度で契約更新が行われるのが一般的です。契約更新では更新料を徴収されるため、2年に1回は家賃以外の支出が生じます。
しかし、借り上げ社宅を選んだ場合は賃貸契約の更新料が発生しないケースがあります。
会社によって異なりますが、会社が更新料を支払ってくれる場合、家賃の一部負担だけで済むため、費用負担を抑えられるのがメリットと言えるでしょう。
メリット5 住宅手当に比べ従業員の負担が増えない
住宅手当をもらった場合はその分給与とされますので税金や社会保険料の負担が増えることになりますが、借り上げ社宅の場合は、給料は増えませんのでそれらの負担が増えません。
従業員が借り上げ社宅を利用するデメリット
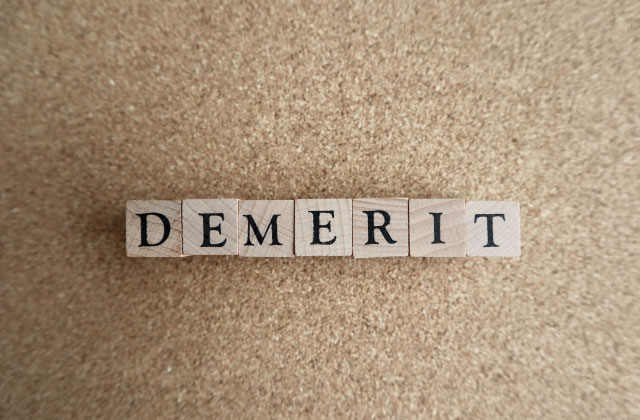
従業員が借り上げ社宅を利用することにはメリットだけではなく、以下のようなデメリットも伴います。
- 自由に物件や場所を選ぶことができない
- 収入額が増えないので社会保障額も増えない
- 退職時に退去しなければならない
それぞれのデメリットを詳しく見ていきましょう。
デメリット1 自由に物件や場所を選ぶことができない
住居手当の場合は立地や間取りなどを自由に選べますが、借り上げ社宅の場合は会社が契約している物件しか選べません。
自由に物件や場所を選べるわけではないため、立地や間取りの条件が悪かった場合には、家賃は抑えられても他の部分に不満が生じる可能性があるという点に注意が必要です。
デメリット2 収入が増えないので社会保障額も増えない
住居手当は給与に上乗せされるので収入や所得額が増えるという特徴がありました。一方、借り上げ住宅は給与からの追加がないためそれらは増えません。
所得額が増えなければ所得税や住民税を抑えられる一方、収入を元に決められる年金といった社会保障額が増えない可能性があります。借り上げ社宅を選ぶことが必ずしも将来のプラスになるとは限らないという点に注意しましょう。
デメリット3 退職時に退去しなければならない
住居手当の場合は会社から現金を支給される仕組みになっています。そのため、仮に会社を退職した場合でも住居手当が出なくなるだけで、契約中の物件から退去する必要はありません。
しかし、借り上げ社宅の場合は会社が契約している物件に住んで家賃の一部を補助してもらう仕組みになっています。そのため、退職した場合は必ず契約中の物件から退去しなくてはならないのもデメリットと言えるでしょう。
借り上げ社宅の家賃相場

借り上げ社宅の家賃は法律上の規定がありません。そのため、企業は家賃を自由に設定することが可能です。しかし、従業員の所得を計算する場合は、賃料相当額の50%以上に設定することによって給与として計上する必要がなくなるため、50%以上で設定されるのが一般的です。
賃料相当額は以下の3つの合計金額で決まります。
- その年度の建物の固定資産税の課税評価額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
参照:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
上記の計算式を使用した場合、賃料相当額の50%は周辺地域の平均家賃のおおよそ10~20%程度となることが多いです。
借り上げ社宅の家賃相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>社宅の家賃相場をご紹介!節税のポイントは国税庁の非課税枠
社宅制度を導入するまでの流れと運用方法

社宅制度の導入が決まった場合は、以下の流れで導入し、運用していくことになります。
- 1.社宅制度の設計をする
- 2.社内で社宅制度導入の決議を行う
- 3.社宅管理規定を準備する
- 4.担当者を決め運用する
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
社宅制度の設計をする
社宅制度は一度導入すると簡単には廃止できません。導入する場合は慎重に判断する必要があるため、社内に専門チームを立ち上げて、導入するメリット・デメリット、賃料設定についてなどを話し合います。
法務・税務面の知識も必要とされるため、弁護士や税理士などのアドバイスを受けながら検討しましょう。
社内で社宅制度導入の決議を行う
社宅制度を設計した後は取締役会にて審議を行います。社宅制度を設計した専門チームも取締役会に参加し、社宅制度の内容を取締役に説明して、認識の共有を図りながら導入を決議します。
社宅管理規定を準備する
取締役会で社宅制度の導入が決まった後、社宅管理規定の準備に移行します。社宅管理規定を作成する理由はトラブル防止のためです。
借り上げ社宅の場合は、従業員だけでなく他の入居者もいるため、他の入居者に迷惑がかかると会社の信用が低下する要因となりかねません。社有社宅の場合は、従業員だけしか利用しませんが、従業員間でトラブルが発生する可能性があります。トラブル防止や社宅の手続きをスムーズに進めるという観点から社宅管理規定を作成しておくことが大切です。
社宅管理規定の作り方はこちらの記事で詳しくご紹介しています。無料の雛形もご用意しておりますので、ご活用ください。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開
担当者を決め運用する
社宅制度を導入すると、物件の選定、入居手続き、家賃の支払い管理、支払調書の提出、契約の更新手続き、解約時の退去手続きなどの管理・運用をする必要があります。
社宅制度の管理・運用する部署は明確に決まっていません。しかし、会社の採用や雇用の管理、制度や環境の整備などを担う人事部が管理・運用するのが一般的です。
普段の業務と並行しながら取り組むことは可能ですが、時期によっては他の業務が多く、並行して行うことが困難な可能性があります。自社で運用しきれない場合は「社宅代行サービス」の利用をも検討しましょう。
借り上げ社宅制度を導入する際の注意点

借り上げ社宅制度を導入する際は、以下の点に注意が必要です。
- 社宅管理規定を作成する
- 企業が物件の賃貸契約を結ぶ
- 従業員から一定額以上の利用料を受け取る
それぞれの注意点を詳しく解説していきます。
社宅管理規定を作成する
社宅管理規定を事前に作成していないと、トラブルが発生しやすいだけでなく、トラブルが発生しても対応が遅れることによって状況が悪化する可能性があります。
トラブルを未然に防ぐ、状況の悪化を防ぐためにも会社と従業員の家賃の負担割合、住居に住むことができる人の範囲、退去条件、責任を負う範囲、規約に違反した場合の対処法などを規定しておきましょう。
企業が物件の賃貸契約を結ぶ
住宅手当では、従業員が契約者となり家賃の全額を支払い、会社は住宅手当として従業員に支給して住居費の負担を軽減します。しかし、借り上げ社宅の場合、会社が契約者となり家賃の全額を支払い、従業員は家賃の一部を会社に支払います。
従業員が個人名義で契約を締結した場合は、社宅制度として認められないことがほとんどです。また、敷金や礼金、火災保険料などの契約に付随して発生した費用を従業員が負担した場合も社宅制度として認められない可能性があるので注意が必要です。
従業員から一定額以上の利用料を受け取る
企業が社宅を利用する従業員から一定以上の家賃を受け取っていない場合は、給与とみなされて家賃相当額を現物支給したと判断される可能性があります。その場合、家賃が非課税対象になりません。
給与とみなされないようにするためには、会社は賃料相当額の50%以上を従業員から受け取る必要があるので注意してください。
社宅の節税効果については以下の記事でも詳しく解説しています。
>>社宅を経費とする節税方法について解説
社内での運用が厳しい場合は「社宅代行サービス」がおすすめ
会社に社宅制度を導入するにあたり管理・運用を社内で完結させすることは可能です。しかし、担当部署の負担が大きくなることで業務に支障が生じる可能性があるので注意してください。また、社宅の数が増えて途中から管理・運用が困難になるケースも少なくありません。
社内での管理・運用が厳しい場合は「社宅代行サービス」の利用をおすすめします。社宅代行サービスとは、社宅を提供する際に必要な物件の確保、契約、解約、入退去管理などの社宅管理業務を外部の業者が代わりに行うことです。外部に委託することで、管理にかかる手間を省き、社宅管理を担う部署の負担を軽減できるでしょう。
社宅代行について詳しく知りたい方は、こちらのページを参考にしてください。
>>社宅代行とは?メリット・デメリットを包み隠さず解説
すでに社宅を導入している場合もこれからの場合も、まずは料金のシミュレーションから。社宅代行サービスの検討をしている方には特におすすめです。
>>今すぐ料金シミュレーションをする
まとめ
福利厚生を充実させる目的で社宅を導入すべきかどうか悩んでいる方も多いと思います。社宅を導入してから後悔しても手遅れなので、事前に社宅を導入するメリットとデメリットをよく理解しておくことが重要です。
この記事には、社宅とは何なのか、会社に社宅を導入するメリットとデメリットなどを分かりやすくまとめています。これから社宅を導入するのであれば、社有社宅よりも借り上げ社宅の方が良いと言えますが、住宅手当の方が良いケースもあるため、双方の違いをよく理解してから導入しましょう。
監修者プロフィール

税理士・公認会計士
中川崇(なかがわたかし)
田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。