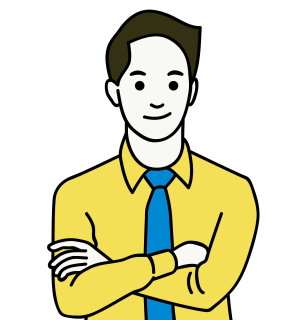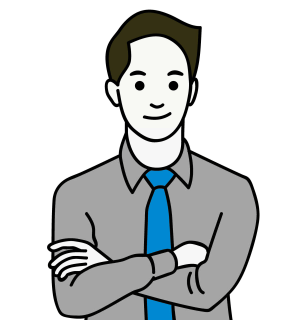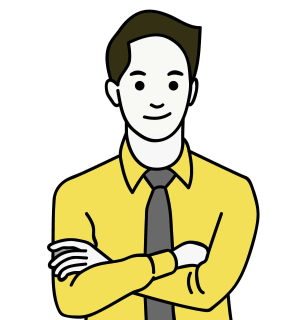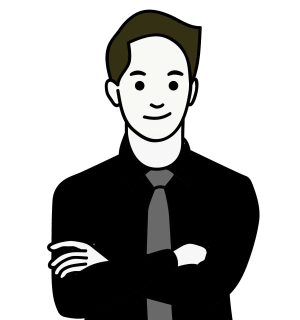はじめに
近年、福利厚生の一環として注目を集める「借り上げ社宅制度」。従業員満足度の向上だけでなく、採用力強化や人材定着にも寄与することから、多くの企業が導入・運用しています。
しかし、借り上げ社宅の契約にあたっては専門的な知識が必要となるほか、煩雑な手続きが発生します。制度の概要や契約プロセスを事前にしっかりと把握しておくことで、スムーズな導入や効果的な運用を目指せるでしょう。
今回は借り上げ社宅の概要や契約の流れ、導入時の注意点など、制度導入を任された担当者向けのお役立ち情報をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、社宅管理の効率化に向けた包括的なサポートサービスを提供しております。まずはぜひ以下の料金シミュレーターをお試しいただき、費用感をチェックしてみてください。
>>料金シミュレーターを試してみる
そもそも「借り上げ社宅」とは

「借り上げ社宅制度」とは、企業が法人名義で賃貸住宅を賃借し、それを社宅として社員に提供する制度のことを指します。自社で社宅を所有・管理するのではなく、不動産会社やオーナーが所有する賃貸住宅を外部から借り上げる形態であることが特徴です。
なお、借り上げ社宅は契約形態や税務上の処理などが通常の賃貸契約とは異なるため、導入の際には事前に制度設計を十分に検討し、社内規定や運用ルールを整備する必要があります。
福利厚生としての位置づけ
借り上げ社宅は、企業が従業員の住環境を支援する目的で提供する「法定外福利厚生」の一種です。法定外福利厚生とは、労働基準法などで定められている「法定福利厚生」(社会保険や労災など)とは異なり、企業が自主的に整備・提供する福利厚生制度であることから、自社の経営方針や人事戦略に基づいて制度内容・運用方法を設計できます。
なお、借り上げ社宅制度においては賃貸契約にかかる初期費用や家賃の一部を企業側が負担するケースが一般的で、従業員の満足度向上を期待できます。また、そのような充実した福利厚生を展開していることによって社員を大切にする企業姿勢をアピールでき、社外に対しても好印象を与えることが可能です。
さらに、都市部や採用競争が激しい業界では、借り上げ社宅の導入が優秀な人材確保に直結するケースも多く見られます。つまり、借り上げ社宅制度は従業員と企業の双方にとって魅力的な福利厚生制度といえるでしょう。
社有社宅や社員寮、住宅手当との違い
借り上げ社宅制度の導入にあたり、社有社宅や社員寮、住宅手当と比較検討している方もいるかもしれません。いずれも「企業が従業員の住居支援を目的として導入する制度」という共通点がありますが、それぞれに異なる特徴があるため、企業の方針や従業員のライフスタイルに応じて適切な制度を選択することが重要です。
ここでは、借り上げ社宅、社有社宅、社員寮、住宅手当の主な特徴を押さえておきましょう。
| 制度名 | 契約形態 | 企業の契約形態 | 従業員の自由度 |
|---|---|---|---|
| 借り上げ社宅 | 企業が民間の賃貸物件を契約し、従業員へ提供 | 賃貸(企業が借主) | 高め(物件選定に関与できるケースもあり) |
| 社有社宅 | 企業が所有する住宅を従業員へ貸与 | 自社所有 | 低め(物件は固定) |
| 社員寮 | 企業が所有する(または借りている)建物に複数の従業員が共同生活 | 自社所有(または賃貸) | 低い(個室がない場合もあり) |
| 住宅手当 | 従業員が自分で住居を契約し、企業が補助金を支給 | なし | 高い(好きな場所に住める) |
民間の賃貸物件を法人契約で借り上げるスタイルの借り上げ社宅とは異なり、社有社宅は企業が自社で所有する住宅を従業員に貸与する制度です。固定資産税や修繕費などの負担は企業側にありますが、長期的な資産運用が可能であるほか、社員同士の交流を促進できるメリットもあります。
また、社員寮は企業が単身者向けに提供する住居施設のことで、食堂や共用スペースを完備しているケースも少なくありません。家賃が相場より安く設定されていることが多く、従業員の経済的負担を軽減できます。
そして、住宅手当は企業が従業員の住居費用の一部を給与として支給する制度です。従業員は自由に物件を選び、個人契約で居住することが可能ですが、原則として給与と同様に課税対象となるため、所得税・住民税・社会保険料の算定に含まれる点に注意する必要があります。
社宅の概要については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅とは?寮や住宅手当との違い、メリット・デメリットまで
借り上げ社宅の契約の基本的な流れ

ここでは、借り上げ社宅の契約における基本的な流れをご紹介します。
1. 社内での導入決議
まず行いたいのが、社内で借り上げ社宅制度の導入を決議することです。経営陣や人事・総務部門などで費用対効果について慎重に検討し、導入の可否を判断します。
2. 社宅管理規定の作成
導入が決定したら、制度運用のための社宅管理規定を作成します。社宅管理規定には主に以下の内容を明記し、制度の公平化や税務処理の適正化を目指しましょう。
- 借り上げ社宅制度の目的と定義
- 入居資格
- 家賃の負担割合(例:企業50%/従業員50%)
- 初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など)の負担区分
- 費用の徴収方法・日割り計算のルール
- 入退去手続きに関するルール・入居期限
- 規定違反への対処法
- 規定の施行日・改定履歴の記録
社宅管理規定の作成については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!
3. 担当者の選定および運用体制の整備
制度設計が整ったら、社宅運用を担う担当者を選定し、社内の運用体制を構築します。物件選定や契約管理、従業員との調整などを一貫して対応できる体制を整えることは、制度の円滑な運用に向けて必要不可欠です。
4. 物件選定
運用体制の整備後は、実際に社宅として提供する物件を選定します。企業が直接選ぶ場合もあれば、従業員が候補物件を提示する方式を採用しているケースもみられます。
5. 賃貸契約の締結
物件が決まったら、企業名義で賃貸契約を締結します。従業員個人ではなく企業が契約主体となることから、契約条件や提出書類、審査基準などが一般の個人契約とは異なるため、詳細について事前にしっかりと確認しておきましょう。
6. 従業員との社宅使用契約
賃貸契約締結後は、従業員との間で社宅使用契約を結びます。社宅の利用条件や注意事項を明記した契約書を取り交わし、企業と従業員の間で認識の齟齬が生じないようにすることが大切です。
7. 入居・管理開始
すべての契約手続きが完了したら、いよいよ従業員の入居開始です。従業員が入居した後は、家賃の支払い管理や契約更新手続き、退去時の原状回復費用の精算など、継続的な運用業務が発生します。
借り上げ社宅の契約時に注目したい5つのポイント

借り上げ社宅制度を円滑に運用するためには、契約時に以下の5つのポイントに注目することが重要です。
- 自社の社宅管理規定とのマッチング
- 初期費用の金額
- 更新方式と更新料
- 火災保険について
- 契約解除の方法や期限、違約金の有無
具体的にどのような点に留意して契約する必要があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
1. 自社の社宅管理規定とのマッチング
借り上げ社宅の契約を進める際には、契約しようとする賃貸物件が自社の社宅管理規定と合致しているかを事前に確認することが大切です。社宅管理規定には入居資格や手続き方法、使用料、禁止事項といった重要なルールが明記されており、これらと契約物件の条件が一致していない場合、後々のトラブルにつながりかねません。
たとえば、社宅管理規定で同居人を許可しているにもかかわらず「単身者限定」の物件を契約することのないようにしましょう。
2. 初期費用の金額
借り上げ社宅の導入にあたってかかる初期費用の金額も、契約前にしっかりと確認しておくとよいでしょう。代表的な初期費用である敷金・礼金・仲介手数料の目安金額は以下の通りです。
- 敷金(原状回復費用の担保):家賃1〜2か月分程度
- 礼金(オーナーへの謝礼):家賃1か月分程度
- 仲介手数料(不動産会社への報酬):家賃1か月分が上限
なお、敷金・礼金・仲介手数料は契約上必ず発生する費用であるため、借り上げ社宅制度においては企業側が全額負担するケースが一般的です。
3. 更新方式と更新料
借り上げ社宅の契約時には、更新方式と更新料にも注目する必要があります。まず、更新方式としては主に「自動更新」と「合意更新」の2パターンがあり、それぞれの特徴は以下の通りです。
【自動更新】
契約期間満了時に特段の申し出がなければ、同条件で自動的に契約が継続される方式です。事務手続きが簡素化されるため、社宅管理の負担が軽減されるメリットがあります。
【合意更新】
契約満了時に貸主・借主双方が改めて契約条件を協議し、合意のうえで更新する方式です。家賃改定や契約条件の見直しを定期的に行える点が魅力ですが、その分、更新手続き時に手間がかかります。
なお、契約更新時に支払う更新料の相場は地域や物件によって異なりますが、「家賃1か月分」が最も一般的です。費用負担者は企業であるケースが多いものの、転勤などの会社都合による更新は企業負担、自己都合による継続利用は従業員負担としている場合もあります。
4. 火災保険について
借り上げ社宅の契約において、火災保険はほぼ必須の条件とされるケースが多いため、契約前にその内容をしっかりと確認しておくことが重要です。特に法人契約の場合、火災や水漏れなどによる損害が発生した際には契約主体である企業が損害賠償責任を負う可能性があるため、補償範囲や保険料の負担区分について確認しておきましょう。
なお、火災保険には建物の損害を補償する「借家人賠償責任保険」や、従業員の家財を守る「家財保険」などがあり、契約内容によって補償範囲が大きく異なります。万が一の際の助けとなる重要な制度なので、以下の点を入念に確認したうえで契約へと踏み切るとよいでしょう。
- 補償対象(建物・家財・第三者賠償など)
- 特約の有無(地震保険、水災補償など)
- 保険料の支払い方法(年払・月払・一括)
- 加入手続きの流れ(契約者・被保険者の区分)
なお、複数の社宅を管理する企業には「包括保険」の活用がおすすめです。これは企業が複数の借り上げ社宅に対して一括で火災保険契約を締結できる制度で、主に以下のようなメリットがあります。
- 契約・更新・解約の手続きが一元化され、社宅管理業務の負担を軽減できる
- 会計処理が簡素化され、経理部門との連携がスムーズになる
- 補償内容の統一化により、従業員間の公平性を確保できる
- 加入漏れの防止により、万が一のリスクに備えやすくなる
包括保険については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>包括保険とは?社宅管理におけるメリットや注意点を紹介
5. 契約解除の方法や期限、違約金の有無
借り上げ社宅の契約解除の方法としては、口頭ではなく書面(郵送・メール・FAXなど)での通知が義務付けられていることが多いため、事前に確認しておくとよいでしょう。また、契約解除の期限は1か月前が一般的ですが、契約によっては2か月前や特定日付までの通知が必要な場合もあるので注意が必要です。
さらに、契約期間満了前の中途解約や予告期間を守らない解約においては、家賃1か月分相当の違約金が発生するケースも少なくありません。違約金の有無や金額は、賃貸借契約書の「特約条項」や重要事項説明書に明記されていることが多いため、契約締結前に必ずチェックしておくことが大切です。
借り上げ社宅の管理業務もチェック

借り上げ社宅の運用にあたっては以下のような管理業務が継続的に発生するため、契約の流れとともに把握しておくことをおすすめします。
【毎月発生する管理業務】
- 家賃の支払い処理
- 社宅使用料(従業員負担分)の徴収
- 給与所得控除の手続き
- 福利厚生費としての損金処理 など
【年単位で発生する管理業務】
- 支払い調書の作成・提出
- 社宅規定の見直し など
【契約更新関連の管理業務】
- 契約更新期日の管理
- 更新条件の精査
- 更新申請手続きと更新料の支払い
- 火災保険契約の更新手続き など
【社宅の退去・解約関連の手続き】
- 退去書類への対応
- 敷金の清算手続き など
借り上げ社宅の管理業務については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅担当者が知っておくべき社宅管理にかかる手続きとは?
借り上げ社宅の契約・管理を円滑に行いたい方へ

ここまで解説した通り、借り上げ社宅の契約にあたっては税務・法務・契約管理などの専門的な知識が不可欠です。また、煩雑かつ専門性の高い業務が継続的に発生するため、特に複数物件を運用する企業では社内リソースのみで対応するには限界があるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、社宅の契約・管理を業務委託できる「社宅代行サービス」の活用です。契約・更新・解約・家賃管理などをまるごと任せることが可能で、企業の社宅担当者の負担を大幅に軽減できます。
LIXILリアルティでは、借り上げ社宅管理の業務負担・コストを削減する社宅代行サービスをご提供しています。これまでに様々な企業の社宅運用をサポートしてきた実績があり、それぞれの企業様の方針に合った入居期限のアドバイスが可能です。
社宅の導入を検討している、社宅管理の見直しを行っている担当者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
>>社宅管理について相談する
>>資料をダウンロード(無料)する
まとめ
借り上げ社宅は法人名義による賃貸契約であることから、手続き手順や内容が通常の賃貸契約とは大きく異なります。契約の流れや注意点を事前にしっかりと把握しておくことで、導入後のトラブル防止につながるほか、従業員に安心して利用してもらえる環境を整えることが可能です。
特に、複数の借り上げ社宅物件を運用している場合や、異動・採用が頻繁に発生する企業においては、借り上げ社宅の契約・管理の煩雑さが大きな負担となるケースも少なくありません。ぜひ社宅代行サービスを強力なパートナーとし、借り上げ社宅制度の戦略的な運用を目指してはいかがでしょうか。