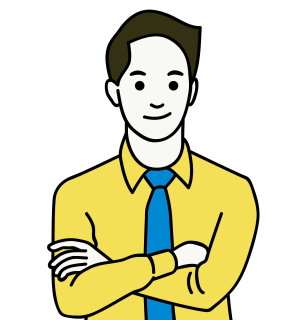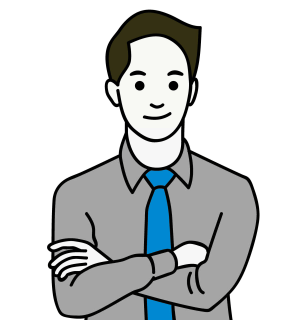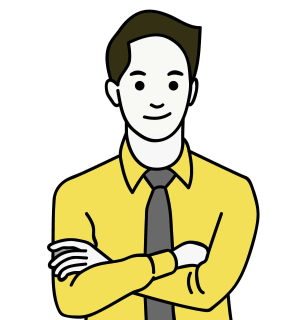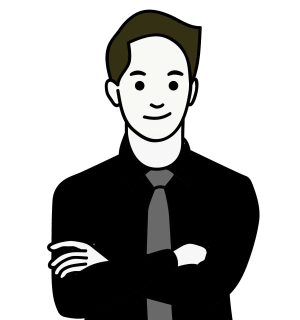はじめに
福利厚生の一環としてこれから社宅制度を導入しようと検討している企業の社宅担当者の中には、どのような手続きが必要なのか気になっている方もいるのではないでしょうか?手続きに不備があった場合、社宅提供のメリットを十分に発揮できない可能性もあるため、社宅制度の導入と継続にはどのような手続きが必要なのかを事前に把握しておくことが重要です。
この記事では、これから社宅制度を導入しようと検討している社宅担当者に向けて、新規契約、月次・年次、契約更新時、解約・退去で必要な借り上げ社宅をベースとした手続きについて解説します。社宅制度の導入を検討している社宅担当者の方は、是非参考にしてみてください。
社宅管理業務の新規契約にかかる手続き

福利厚生の一環として社宅制度を新規に導入する場合、いくつか手続きを行わなくてはなりません。手続きに不備があった場合、社宅制度の導入をスムーズに行うことができないため、どのような手続きが必要なのかを事前に把握しておくことが重要です。
社宅制度を導入する際の新規契約にかかる主な手続きは「物件の手配」「新規契約の手続き」の大きく2つに分類されます。それぞれの手続きを詳しく見ていきましょう。
物件の手配
社宅制度を導入する際は、社宅として利用する物件をまずは手配しなくてはなりません。物件を手配する際に必要な手続きは以下の5つです。
- 社宅利用者との連絡
- 不動産業者に物件の斡旋依頼
- 契約条件の精査
- 希望物件へ入居の申込み
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
社宅利用者との連絡
まずは社内にどれだけ社宅の利用を希望している従業員がいるのかという実態を把握します。社内のメールや掲示板に社宅制度の導入を開始する旨を共有する、アンケート調査を実施してどの程度の従業員が社宅利用を希望しているのかを確認しておきましょう。
契約条件の精査
不動産業者に斡旋された物件の賃料が高すぎる、部屋が広すぎる場合、企業規定と合っていないという理由で承認が得られない可能性があります。承認を得るために、契約条件と企業規定と合っているかどうかを精査・調整を行います。
希望物件へ入居の申込み
企業規定と契約条件を踏まえた上で、不動産業者から斡旋された物件の中から社宅に適した物件を選びます。選んだ物件の入居申込みを行えば、物件の手配は完了です。
新規契約の手続き
物件の手配が完了した後は、従業員や物件の貸主と新規契約の手続きを行います。新規契約を行う際に必要な手続きは以下の5つです。
- 入居申請と承認
- 契約手続き
- 契約書類の回収と保管
- 契約金の算出・支払い
- 引越し手続き
- 入居者登録
- 入居者個人負担額計算
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
入居申請と承認
社宅の利用を希望する従業員に入居申請書を提出してもらい、入居申請書に基づいて担当部署が承認を行います。
契約手続き
賃貸物件の貸主と賃貸契約を締結します。賃貸契約の締結では、重要事項の説明を受けて、重要事項説明書と契約書に署名・押印を行います。火災保険への加入や家賃保証会社との契約を求められるケースもあるため、物件ごとにどのような契約手続きを行うのか事前に確認しておきましょう。(重要事項説明は実際に入居する社員の方が受けることが多いです。)
契約書類の回収と保管
契約手続きで作成した重要事項説明書と賃貸契約書は、契約内容を確認する際に必要なだけでなく、何らかのトラブルが生じた場合の証拠となります。紛失しないように社宅担当者が契約書類の確認・保管を行います。
契約金の算出・支払い
賃貸契約の締結には、敷金・礼金・仲介料・初月の家賃などの初期費用がかかります。それらを全て算出し、経理担当に支払い処理を依頼します。初期費用の支払いが完了すれば、鍵を受け取ることが可能です。
引越し手続き
初期費用の支払い後は、いよいよ引越し手続きです。社宅担当者は、社宅に入居する従業員と話し合いながら引越しの見積、引越し業者の選定、引越し日の確定などの手続きを行います。
入居者登録
社宅の入居が決まった従業員の入居者登録を行います。入居日、入居の理由、入居形態といった必要な情報を整理して管理します。
入居者個人負担額計算
社宅にかかる費用を従業員は一部負担することになります。社宅担当者は、社宅管理規定に基づいて従業員の負担額を計算して管理します。必要に応じて経理担当への報告も行わなくてはなりません。
社宅管理業務の月次でかかる手続き
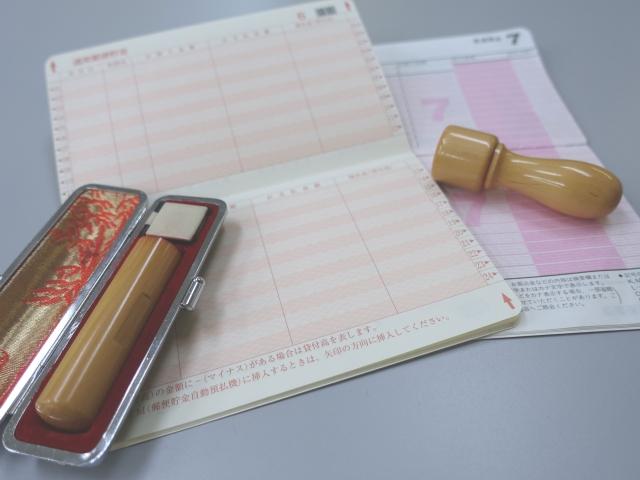
社宅担当者は、新規契約の手続き以外に月次手続きも行う必要があります。月次手続きは「家賃の支払い」「給与所得控除」の大きく2つに分類されます。それぞれの手続きを詳しく見ていきましょう。
家賃の支払い
社宅担当者は毎月社宅として利用している物件の賃料を支払わなくてはなりません。家賃を支払う際に必要な手続きは以下の通りです。
- 家賃支払額の精査
- 送金データの処理
- 家賃の送金
家賃支払額の精査
家賃支払額が誤っていた場合、後でトラブルに発展するため、毎月の家賃支払額に誤りがないか確認します。間違いがあればすぐに修正し、正確な情報を維持します。
送金データの処理
振込先が誤っていた場合、後でトラブルに発展するため、送金データに誤りがないかを確認しながら振込先を管理します。間違いがあればすぐに修正し、正確な情報を維持します。
家賃の送金
家賃支払額の精査、送金データの処理が完了した後は、それらの情報を経理担当者に渡します。経理担当者は受け取った情報に基づいて出金処理を行います。
給与所得控除
社宅担当者は家賃を一部負担する従業員の給与所得控除の手続きも行う必要があります。給与所得控除の際に必要な手続きは以下の通りです。
- 個人負担額の精査
- 給与所得控除の処理
個人負担額の精査
従業員がいくら家賃を負担するのかを精査します。間違いがあった場合、給与所得控除を受けられないため、すぐに正しい情報に修正しなくてはなりません。
給与所得控除の処理
社宅担当者は、精査した個人負担額の情報を経理担当者に渡します。情報を受け取った経理担当者が給与所得控除の処理を行えば、月次処理は完了です。
社宅管理業務の年次でかかる手続き

社宅担当者は年次手続きも行う必要があります。年次手続きは支払い調書関連だけですが、最も負担の大きな業務と言われています。支払い調書について詳しく見ていきましょう。
支払い調書
支払い調書とは、1月1日から12月31日までに支払った費用についてまとめた書類です。支払い調書に必要な手続きは以下の通りです。
- 支払い調書の準備・作成
- 支払い調書の提出
支払い調書の準備・作成
1月1日から12月31日までに支払った住宅関連の費用に基づきながら支払い調書を作成します。作成するのは不動産使用料等の支払い調書、非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払い調書、不動産等の売買又は貸付けの斡旋手数料の支払い調書のいずれかです
支払い調書の提出
該当する支払い調書に必要事項を記載した後は、会社の所在地を管轄する税務署に提出します。支払い調書の提出期限は、1月31日とあまり余裕がないので注意しましょう。
社宅の契約更新時にかかる手続き
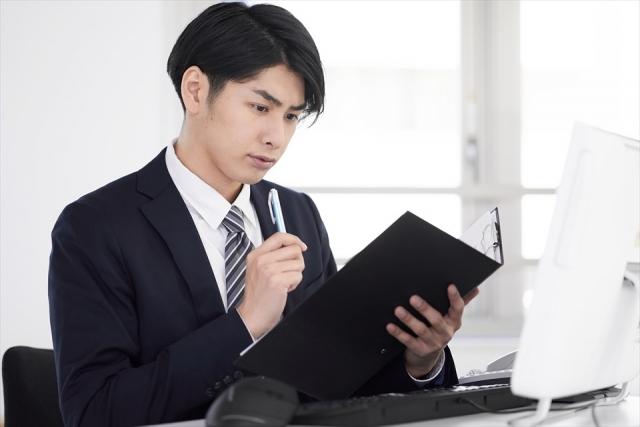
社宅担当者は契約更新を迎えた場合、以下のような手続きを行う必要があります。
- 契約更新期日の管理
- 更新条件の精査
- 更新申請と承認
- 賃貸契約の更新手続き
- 契約更新料支払い
- 契約更新書類の回収と保管
契約更新期日の管理
賃貸契約は2年に1回の頻度で更新を迎えるのが一般的です。契約時期によって契約更新期日が異なるため、物件ごとの契約更新期日を把握しておく必要があります。
更新条件の精査
賃貸契約を更新する際は、更新料を支払う、家賃の値上げが生じる可能性があります。更新条件が悪い場合は契約を見直す必要があるため、更新条件の精査を行います。
更新申請と承認
更新条件の精査を行って問題がなければ、社内で更新申請を行います。更新申請の承認を得られた場合、次のステップに移行します。
賃貸契約の更新手続き
承認を得られた後は、貸主と賃貸契約の更新手続きを行います。賃貸契約の更新手続きにあわせて火災保険や家賃保証の更新も必要になる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
契約更新料支払い
賃貸契約の更新手続きでは、更新料、手数料等の費用を支払います。火災保険や家賃保証を更新する場合は、保険料や手数料の支払いもあります。
契約更新書類の回収と保管
新規契約で重要事項説明書と賃貸契約書を社宅担当者が管理したのと同様、契約更新に関する書類も回収して保管します。
社宅の退去・解約に関わる手続き

社宅担当者は転勤や退職に伴う退去・解約が生じた場合、以下のような手続きを行う必要があります。
- 退去申請を受け取る
- 解約の通知
- ルームチェック
- 退去手続きを行う
- 敷金精算の手続き
- 入居者負担の徴収
- 解約書類の作成・提出・保管
退去申請を受け取る
退去予定の従業員が作成した退去申請書を受け取ります。退去申請書を受け取る際は、退去予定がいつなのかしっかり確認しましょう。一度提出した解約通知はキャンセルできないことが殆どなので、通知する際は慎重に行うよう注意が必要です。
解約の通知
退去申請書を受け取った後は、貸主又は管理会社に解約を通知します。解約通知から何ヶ月で解約されるかは契約内容によって異なるため、契約書に基づいて退去予定日から逆算して解約を通知しましょう。
ルームチェック
従業員が退去する際は、忘れ物があった場合や従業員が正しく部屋を使用しなかったことが原因で修繕費用を追加徴収された場合にトラブルに発展する可能性があります。万が一に備えるためにも、必ず退去後の部屋を確認しましょう。
退去手続きを行う
社宅担当者は、退去に立ち会うための日程調整、従業員から受け取った鍵の返却、原状回復費用が適正なのか精査します。
敷金精算の手続き
月の途中で解約となる場合は日割り家賃の返金、原状回復費用によっては敷金の返却又は追加請求が発生する可能性があります。追加費用は誰から徴収するのかもこの時点で明確にします。
入居者負担の徴収
従業員が正しく部屋を使用しなかったことが原因で修繕が必要になった場合、入居者負担となる可能性があります。入居者負担とする場合、トラブルに発展する可能性があるため、どのようなケースで追加徴収するのかを事前に決めておきましょう。
解約書類の作成・提出・保管
契約関係、更新関係の書類を保管したのと同様、社宅担当者は退去・解約関連の書類を作成・提出・保管する必要があります。従業員が退去したから書類を破棄しても良いというわけではないので注意しましょう。
社宅代行サービスなら業務8割を削減

社宅管理には数多くの手続きが必要なので、社宅担当者の負担はかなり大きいと言えます。しかし、社宅代行サービスを利用すればこれらの負担を大幅に軽減できます。社宅代行サービスとは何なのか、社宅代行のメリットについて詳しく見ていきましょう。
社宅代行サービスとは
社宅代行サービスとは、社宅制度を導入する際に必要な業務を企業から委託を受けた社宅代行会社が代わりに行ってくれるサービスです。
社宅代行サービスを提供している事業の1社であるLIXILリアルティでは、以下のような業務を任せることが可能です。
- 新規・更新・解約などの主要業務
- 毎月の家賃送金
- 支払い調書のデータ整理
- 社宅業務に付随する業務
社宅関連業務の80%以上を任せられるため、社宅担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
社宅代行のメリット
社宅管理を社内で行う場合、人材を確保するもしくは従業員の担当業務を増やして対応することになります。しかし、人材の確保には費用がかかる、担当業務を増やすと従業員の不満が募る可能性があります。
社宅代行サービスを依頼すれば、報酬を支払わなくてはならないものの、無駄を省くことによるコスト削減が期待できる、社宅担当者の負担を軽減することによって本来の業務に専念できるでしょう。
LIXILリアルティの社宅代行
企業側の立場にたった社宅代行
LIXILリアルティの社宅代行サービスは『企業側の立場にたった社宅代行』をコンセプトとしています。それは、LIXILリアルティの社宅代行サービスが『企業のニーズから生まれ』、そして『企業が作った』サービスだからです。また、社宅業務ノウハウの多くは、LIXILと委託契約法人・企業様の総務課、社宅担当者様等のニーズが原点となっています。これにより、当社では『企業側にたった社宅代行』を実現、不動産賃貸・仲介会社視点ではなく企業側視点で企業様にサービスをご提供しています。
(引用URL:https://syataku.lixil-realty.com/)
LIXILリアルティの強み
社宅業務のコストダウン
LIXILリアルティの社宅代行サービスなら、大幅な社宅業務のコストダウンを実現できます。
賃貸借契約書を丁寧に精査し、原状回復費用見積書の精査・ご提案を行い、高い敷金の返還率を目指しています。駐車場管理・マンスリー手配・事務所等送金管理・引越手配業務…などその他付随業務を提供することが可能です。お客様にご納得いただけるよう、削減効果と社宅代行の費用対効果を検証した報告書を提出します。
豊富な物件の量
全国の提携不動産ネットワークを構築。エリア内の複数会社より、物件情報を豊富にご提供いたします。LIXILリアルティは物件紹介をいたしますが、賃貸仲介契約は、弊社ネットワークの不動産会社で対応いたします。そのため、他社不動産会社と競合関係とならず、大手不動産会社をはじめとした「業界の垣根を越えた」ネットワークを実現。ネットワークから提供する物件はもちろん、異動社員が自分で見つけてきた物件も対応可能です。
柔軟なサービス対応
蓄積されたノウハウでリーズナブルなサービス提供を心がけています。一戸からでも対応可能で、企業ニーズに即した「カスタマイズ」対応が当社の強みです。また、企業様に対するリスクを軽減できるよう、お預けした敷金などの債権担保の管理やマイナンバーにかかる個人情報の取り扱い基準を定め、情報の漏洩・改ざん・紛失・破壊・不正アクセスの防止の徹底を行っております。企業様及びグループ会社様の窓口を一本化し、専任担当者が業務のお手伝いをします。
大幅な業務の削減
LIXILグループのアウトソーシングノウハウで社宅管理業務の80%削減を実現いたします。経験豊富なスタッフが業務全般を代行するので、高い業務品質を享受できます。社宅業務の時間が削減でき、企業様は本来のコア業務に時間を費やすことができます。
詳しい内容はこちらからご覧ください。
まとめ
社宅制度を社内に導入することによって福利厚生が充実するため、従業員の満足度を高めることが可能です。しかし、社宅制度を導入した場合、社宅担当者は数多く手続きを行わなくてはなりません。
社宅担当者の業務負担が増えると、従業員の不満が募る、業務効率の低下につながる可能性があるので注意が必要です。社宅代行サービスを利用することで、社宅管理業務の80%以上を任せられるため、従業員の負担を軽減できる、コストを削減できる、業務効率の向上が期待できるでしょう。