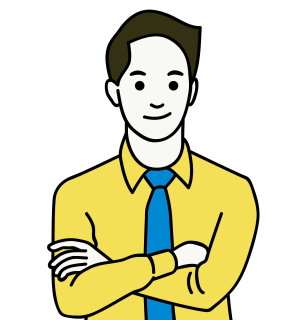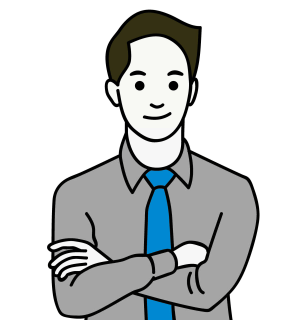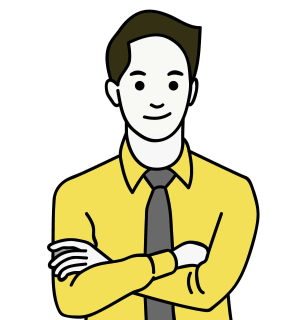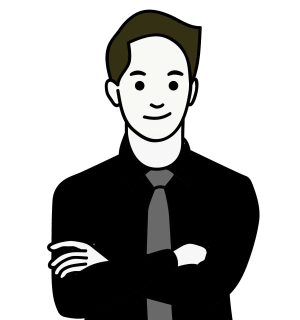はじめに
社宅制度は人材確保・定着率の向上や節税効果といったメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたっては多くの企業が頭を悩ませています。特に税務上の取り扱いは専門的で煩雑な業務を伴うため、「社宅控除の仕組みを正しく理解したい」と考える社宅担当者も多いことでしょう。
そこで、今回は課税・非課税の判断基準や「賃貸料相当額」の算定方法、経理処理の仕訳対応など、社宅控除に関する基礎知識を詳しくまとめました。さらに、社宅制度を円滑に運用するためにぜひ利用したい「社宅代行サービス」の魅力についても併せてご紹介します。
社宅制度の円滑な運用に向けて、ぜひ参考にしてみてください。
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、導入コストを事前に把握できる料金シミュレーターをご用意しております。ぜひ一度お試しください。
>>料金シミュレーターを試してみる
「社宅控除の正しい理解」が制度運用の要

企業が従業員に対して社宅を提供する制度は、福利厚生の充実や人材確保・定着の促進、さらには税務上のコスト最適化といった観点から、多くの企業で導入されています。
一方で、社宅制度の運用には経理処理の複雑さが伴うため、経理・人事・総務担当者の間では次のような悩みを抱えるケースが少なくありません。
- 社宅控除の課税・非課税の判断基準が曖昧で、処理に自信が持てない
- 賃貸料相当額の計算方法が複雑で、正確な算出に不安がある
- 給与明細や仕訳処理において、社宅関連の記載方法が統一されていない
こうした背景から、社宅制度を適切に運用するためには「税務上のルール」を正しく理解し、社内規程や運用フローを整備することが不可欠です。制度の透明性を高めることで、従業員にとっても企業にとっても安心して利用できる仕組みとなり、福利厚生の効果を最大限に発揮することができます。
社宅控除の基本|課税・非課税の判断基準について

社宅制度を適切に運用するうえで、まず押さえておきたいのが「社宅控除の課税・非課税の判断基準」です。従業員負担額が「賃貸料相当額」より少ない場合、その差額は給与として課税され、所得税や住民税の負担が増加します。
そのため、従業員から徴収する家賃がどの程度であれば非課税となるのか、その根拠となる「賃貸料相当額」の考え方を正しく理解することが重要です。ここからは、その基礎知識について詳しく見ていきましょう。
まず押さえておきたい「賃貸料相当額」の基礎知識
「賃貸料相当額」とは、従業員に貸与する社宅が市場で貸し出された場合に相当する家賃水準を、一定の算式に基づいて算出したものです。国税庁の定める基準により、以下の3つの計算式で求めた合計額が「賃貸料相当額」となります。
- 1. 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
- 2. 12円×【建物の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)】
- 3. 敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
この3つを合計した金額が「賃貸料相当額」となり、従業員から徴収する家賃がこの額以上であれば非課税、未満であれば差額が給与課税対象となります。
たとえば、建物の固定資産税課税標準額が10,000,000円、建物の総床面積が100㎡、敷地の固定資産税課税標準額が20,000,000円の場合の賃貸料相当額は以下の通りです。
- 10,000,000円×0.2%=20,000円
- 12円×(100㎡÷3.3㎡)=約364円
- 20,000,000円×0.22%=44,000円
合計:64,364円
非課税となる条件【従業員に社宅を貸し出す場合】
社宅を従業員に貸与する場合、一定の家賃を従業員から徴収していれば給与として課税されないという取り扱いが認められています。これは、社宅制度が福利厚生の一環として合理的に運用されることを前提とした税務上のルールです。
具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
- 従業員から徴収する家賃が「賃貸料相当額」の50%以上であること
国税庁が定める「賃貸料相当額」の算式で算出した金額の半分以上を従業員が負担していれば、給与課税の対象外となります。 - 社宅の提供が福利厚生の一環として合理的に行われていること
単なる給与の一部としてではなく、従業員の生活支援や人材確保・定着を目的とした合理的な福利厚生制度として提供されていることが必要です。 - 社宅の使用が業務上の必要性に基づいていること(勤務地の都合など)
たとえば勤務地が遠方で通勤が困難な場合や、転勤に伴う居住支援など、業務上の必要性に基づいて社宅が貸与されていることが条件となります。
これらの条件を満たすことで、従業員にとっては給与課税の対象外となり、企業にとっても税務上のリスクを回避しながら社宅制度を運用することが可能になります。
非課税となる条件【役員に社宅を貸し出す場合】
役員に社宅を貸し出す場合、非課税とするには「賃貸料相当額以上の家賃を役員から徴収していること」が必須です。 この「賃貸料相当額」の計算方法は社宅の規模や所有形態によって異なるため、正しい理解が欠かせません。
ここでは、「小規模な住宅」に該当する場合・しない場合の賃貸料相当額について解説します。
「小規模な住宅」の場合の賃貸料相当額
「小規模な住宅」とは、以下の条件を満たす住宅を指します。
- 法定耐用年数が30年以下の建物:床面積132㎡以下
- 法定耐用年数が30年超の建物:床面積99㎡以下
この場合、従業員に社宅を貸し出す場合と同様に、次の3つの計算式で求めた合計額が「賃貸料相当額」となります。
- 1. 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
- 2. 12円×【建物の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)】
- 3. 敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
「小規模な住宅」に該当しない場合の賃貸料相当額
社宅が「小規模な住宅」に該当しない場合は、所有形態によって計算方法が異なります。
1.自社所有の社宅の場合
(建物の固定資産税評価額×12%)+(敷地の固定資産税評価額×6%)÷12
※法定耐用年数が30年超の場合は、建物部分に「10%」を乗じます。
2.借り上げ社宅(会社が賃貸契約を結ぶ)の場合
以下のいずれか高いほうが賃貸料相当額となります。
- 会社が大家に支払う家賃×50%
- 上記1の算式による金額
賃料相当額の計算方法については以下の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>役員及び従業員に社宅などを貸した際の賃料相当額の計算方法
非課税扱いなら「社会保険料の負担軽減」にもつながる

社宅制度を導入する企業にとって、従業員の家賃負担が「賃貸料相当額」の50%以上であれば非課税扱いとなるというルールは、税務上のメリットだけでなく社会保険料の面でも大きな効果をもたらします。
というのも、社会保険料は「標準報酬月額」を基準に算定されます。通常、給与課税となる社宅貸与分は「現物給与」として算入されるため、従業員の給与額が増えた扱いとなり、その分、健康保険料や厚生年金保険料の負担も増加する仕組みです。
しかし、非課税扱いとなる場合はこの社宅貸与分が算定基礎に含まれません。つまり、標準報酬月額が増えないため、従業員・企業双方の社会保険料の負担増を防ぐことが可能です。
この仕組みにより、社宅制度は単なる福利厚生にとどまらず、税務・社会保険の両面でコスト最適化を実現する重要な制度といえます。
社宅控除における経理処理・仕訳の具体例

社宅制度を導入する企業では、企業負担分・従業員負担分・課税対象となる場合の給与計上を正しく仕訳することが大切です。誤った処理は税務リスクや社会保険料の算定ミスにつながるため、以下のような仕訳例を押さえておく必要があります。
企業負担分の処理方法
会社が社宅の家賃を大家へ直接支払う場合は、以下のように仕訳します。
【仕訳例】
- 借方:地代家賃(または福利厚生費) 80,000円
- 貸方:現金預金 80,000円
ここで注意すべき点は、共益費も地代家賃に含めることです。そして、住宅の貸付は消費税法上「非課税取引」に該当するため、消費税の計上は不要である点もしっかりと認識しておきましょう。
従業員負担分の処理方法
従業員から社宅使用料を徴収する場合は、以下のように仕訳します。
【仕訳例】
- 借方:現金預金 30,000円
- 貸方:雑収入(または地代家賃) 30,000円
また、給与から天引きする場合は「給与控除」として処理し、給与明細に明記して透明性を確保することが重要です。これにより従業員にとっても安心感が生まれ、社宅制度の信頼性が高まります。
課税対象となる場合の給与計上方法
従業員負担が「賃貸料相当額」の50%未満の場合、その差額は給与課税対象となり、以下のように仕訳します。
【仕訳例】
- 借方:給与手当 20,000円
- 貸方:未払費用(または現金預金) 20,000円
この金額は源泉所得税・住民税・社会保険料の算定基礎に含まれるため、給与計算に必ず反映させる必要があります。課税対象となるか否かの判断は、税務上だけでなく社会保険料の負担にも直結するため、慎重な処理が求められます。
社宅制度を円滑に運用したいなら

社宅制度は従業員の福利厚生や人材定着に大きな効果をもたらす一方で、課税・非課税の判断、賃貸料相当額の算定、経理処理といった複雑かつ専門的な実務を伴います。そのため、社宅制度を円滑に運用するためには、専門的な知識と正確な処理を継続的に行う体制が不可欠です。
しかし、これらを社内だけで完結させようとすると膨大な工数がかかり、税務リスクや従業員への説明不足につながる恐れがあります。
そこで有効なのが、社宅代行サービスの活用です。社宅代行サービスを利用すれば、煩雑な契約・更新手続きや税務処理、従業員への説明までを専門的にサポートしてもらえるため、企業は本来の業務に集中できます。さらに、法令改正や税務ルールの変更に対して迅速に対応できる点も大きなメリットです。
もし現在委託している社宅代行サービスのサポート面に不安や不満を抱えている場合は、業者の変更を検討するのもひとつの方法です。サービス品質やサポート体制は業者によって差があるため、自社のニーズに合った代行会社を選び直すことで、より安心して社宅制度を運用できます。
社宅代行サービスを利用するメリットや費用、選び方については以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
>>借り上げ社宅の運用を社宅代行会社に委託するメリットや費用、選び方
社宅代行サービスを導入する流れについては以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
>>社宅代行の導入はめんどくさい?契約の流れやサービス選びのコツなど
実績豊富な代行サービスをお探しならLIXILリアルティへ
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、企業の社宅運用に必要不可欠である以下のようなサポートを提供しております。
- 社宅契約・更新・解約などの事務手続きの一括代行
- 賃貸料相当額の算定や課税・非課税判断のサポート
- 経理処理・給与計算への反映を正確に行うための運用支援
- 社員向け説明資料や社内規程整備の支援
なお、利用料金については企業規模や契約数に応じてシミュレーション可能で、導入前にコストを把握できる点も大きな安心材料となります。
まとめ
社宅制度の運用において特に重要となるのが、「社宅控除の課税・非課税の判断基準」です。まずは「賃貸料相当額」の算出方法を正しく理解し、従業員・役員それぞれに適用される条件をしっかりと把握することが欠かせません。
さらに、非課税扱いとなるか否かは税務上の取り扱いだけでなく、社会保険料の負担にも直結します。誤った処理は従業員・企業双方に不利益をもたらすため、経理仕訳や給与計算への反映まで含めて慎重に対応する必要があります。
もし「社内での対応に不安がある」と感じる場合は、社宅代行サービスの活用がおすすめです。専門家のサポートを得ながら社宅制度を円滑に導入・継続し、福利厚生の効果を最大限に発揮しましょう。