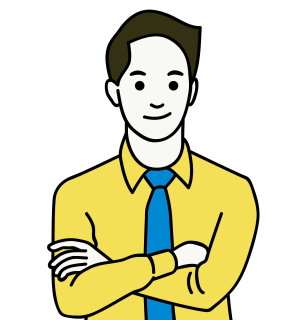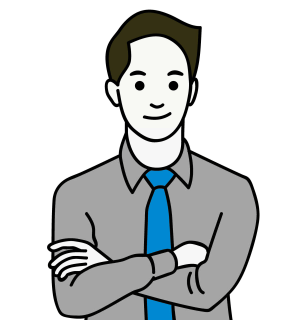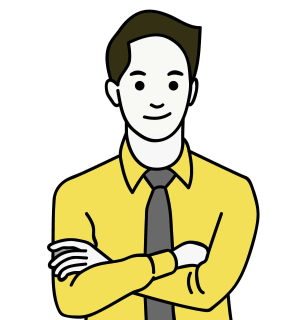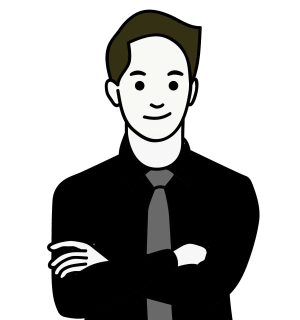はじめに
企業の社宅担当者のなかには、「社宅の退去命令はどのような場合に認められるのか」と気になっている方もいることでしょう。
退去命令の可否は、社宅の種類や法的な扱いによって大きく変わります。誤った判断は従業員とのトラブルにつながるため、正しい知識と適切な対応が欠かせません。
今回は社宅の退去命令に関する基礎知識に触れながら、退去命令が認められやすいケースや実務フロー、トラブル対策について詳しく解説します。社宅管理をより安全かつスムーズに進めるための判断材料として、ぜひお役立てください。
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、社宅運用に必要な業務をワンストップでサポートしております。まずは、以下のシミュレーターで委託費用の目安をぜひご確認ください。
>>料金シミュレーターを試してみる
社宅の退去命令に関する基礎知識

社宅は企業が従業員に提供する住まいであり、一般の賃貸物件とは法的な扱いが異なるケースが多くあります。そのため、退去命令がどこまで認められるのか、どのような根拠で命じられるのかを正しく理解しておくことが大切です。
まずは、社宅の種類ごとに異なる法的な位置づけを整理し、退去命令の可否を判断するうえで押さえておきたい基本知識を確認していきましょう。
社宅の種類によって法的扱いが異なる
「社宅」と一口にいっても、実際には複数の形態が存在し、それぞれで法律上の扱いが大きく異なります。退去命令が認められるかどうかは、この「社宅の種類」によって左右されるため、まずは自社の社宅がどの分類に該当するのかを把握することが欠かせません。
ここでは、代表的な3つの形態について解説します。
借り上げ社宅
最も一般的なのが、会社名義で賃貸契約を結ぶ「借り上げ社宅」です。この場合、賃貸借契約の主体はあくまで会社であり、従業員は会社から住居の使用を許可されている立場に過ぎません。
従業員自身には賃借人としての法的権利はなく、退去に関する判断権限は基本的に会社側にあります。従業員は「会社の契約物件を利用しているだけ」という位置づけになる点が特徴です。
社有社宅
会社が所有する建物を社宅として提供する「社有社宅」の場合、法的には「使用貸借」に近い扱いとなります。使用貸借とは無償で物を貸す契約形態のことで、この場合も契約主体は会社です。
従業員は会社の資産を使用させてもらっている立場であり、賃借人としての強い権利は認められません。場合によっては、会社の就業規則や社宅規程に基づいて退去命令が出されるケースもあります。
従業員名義の賃貸(住宅手当型)
従業員自身が賃貸契約を結び、会社が住宅手当を支給する形式は、一般的には「社宅」には該当しません。契約主体は従業員本人であり、従業員は賃借人としての法的権利を有します。
そのため、会社が従業員に対して退去を命じることはできず、退去に関する判断は従業員と貸主との契約関係に基づいて行われます。
社宅の概要については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅とは?寮や住宅手当との違い、メリット・デメリットまで
「借地借家法」が適用されるケース・されないケース
社宅の退去命令がどこまで認められるかは、借地借家法が適用されるかどうかで大きく変わります。「借主を強く保護する法律」である借地借家法が適用される場合、貸主である会社は簡単に退去を求めることができません。
そのため、社宅がどの法的枠組みに該当するのかを見極めることが、退去命令の可否を判断するうえで重要なポイントとなります。
借地借家法が適用されないケース(=退去命令が比較的容易)
次のような場合、社宅は「賃貸借契約」ではなく「使用貸借」や「福利厚生としての提供」と判断されることが多く、借地借家法は適用されません。
- 会社名義の借上社宅 :賃貸借契約の主体は会社であり、従業員は会社から使用を許可されている立場にとどまります。
- 会社所有の社有社宅 :法的には使用貸借に近い扱いとなり、従業員は会社の資産を利用しているにすぎません。
- 労務提供と密接に結びつく社宅(住み込み管理人・作業員宿舎など) :住居提供が業務遂行の一部とみなされ、賃貸借として扱われない傾向があります。
これらのケースでは借地借家法の保護が及ばないため、会社側は比較的スムーズに退去を求めることができます。
借地借家法が適用されるケース(=退去命令が難しくなる)
一方、次のような場合は社宅が「実質的に賃貸借契約」とみなされる可能性があり、借地借家法が適用されることがあります。
- 従業員が市場相場に近い使用料を支払っている場合 :使用料が「賃料相当の対価」と判断され、一般の借家と同様に扱われる傾向があります。
- 福利厚生としての性質が弱く、一般賃貸と同様の運用になっている場合 :実態から賃貸借と評価されることがあり、会社側の裁量は大きく制限されます。
- 従業員名義の賃貸(住宅手当型) :契約主体は従業員本人であるため、会社は退去命令を出す権限を持ちません。借地借家法が完全に適用されるケースです。
借地借家法が適用される場合、会社が退去を求めるには「正当事由」が必要となり、さらに退去期限として6か月以上の猶予を設けることが義務づけられています。また、社宅規程などに記載された「退去させる」旨の条項であっても、借地借家法に反する内容は無効と判断される可能性があります。
社宅の退去命令が認められやすい5つのケース

ここまで見てきた法的な前提を踏まえると、社宅の退去命令が認められるかどうかは「社宅の種類」や「借地借家法の適用有無」によって大きく左右されることがわかります。そのうえで、実務では次の条件を満たす場合に退去命令が認められやすい傾向がある点も、しっかりと認識しておくことが大切です。
- 退職・定年退職
- 異動・転勤・配置転換
- 社宅制度の廃止・縮小
- 規程違反・迷惑行為
- オーナーとの契約終了(借り上げ社宅の場合)
これらは社宅制度の目的や利用実態から見ても、退去の合理性が高いと判断されやすい傾向です。それぞれのケースについて、以下で詳しく解説していきます。
1. 退職・定年退職
社宅はあくまで従業員として勤務していることを前提とした福利厚生であり、雇用関係が終了したあとも住み続ける合理性は高くありません。退職や定年退職に伴う退去命令は、法的にも実務的にも認められやすいケースといえます。
2. 異動・転勤・配置転換
社宅には「勤務地の近くで生活できるようにする」という目的があります。そのため、異動や転勤によって勤務地が変わり、社宅を利用する必要性がなくなった場合も退去命令が認められやすいでしょう。特に勤務地が遠方になる場合は社宅利用の前提が崩れるため、退去の合理性が高いと判断されます。
3. 社宅制度の廃止・縮小
企業の方針変更により、社宅制度そのものを廃止したり、対象者を縮小したりするケースもあります。この場合も退去命令は可能ですが、従業員の生活に直結する問題であるため、十分な説明と猶予期間の確保が不可欠です。突然の退去命令はトラブルにつながりやすいため、段階的な移行措置が求められます。
4. 規程違反・迷惑行為
従業員が社宅規程に違反した場合や、近隣住民とのトラブルなどの迷惑行為がある場合も、退去命令が認められることがあります。ただし、いきなり退去を求めるのではなく、まずは注意喚起や改善指導を行い、それでも改善されない場合に退去命令へ進むという段階的な対応が必要です。
5. オーナーとの契約終了(借り上げ社宅の場合)
借り上げ社宅では、企業側がオーナーとの賃貸借契約の当事者となっています。そのため、契約期間の満了や更新拒絶などによってオーナーの契約が終了した場合、従業員に退去を求めざるを得ません。従業員は賃借人ではないため、会社側の契約終了に伴う退去命令は比較的認められやすいといえます。
社宅の退去命令を出す際の実務フロー
社宅の退去命令は従業員の生活に大きな影響を及ぼすため、企業側には「根拠の明確化」と「丁寧な説明」が欠かせません。対応を誤るとトラブルにつながりやすく、場合によっては法的リスクを招くこともあるため注意が必要です。
ここでは、社宅担当者が押さえておくべき実務フローについて確認しておきましょう。
1. 事前準備:規程・契約書・社内ルールの確認
社宅の退去命令を出す前に、まずは社宅制度に関わる基本情報を整理し、次の3点をしっかりと確認しておくことが大切です。
- 社宅規程の内容 :社宅規程に「退去事由」「退去期限」「原状回復の扱い」が明記されているかを確認します。規程が曖昧なまま退去命令を出すと従業員との認識のズレが生じやすく、トラブルの原因になります。
- 契約形態 :前述の通り、借り上げ社宅か社有社宅か、あるいは従業員名義の賃貸かによって、借地借家法の適用範囲が大きく変わります。退去命令の難易度に直結するため、契約形態の把握は必須です。
- 就業規則・社内ルールとの整合性 :退職時の退去期限などは就業規則に定められているケースも多く、社宅規程との整合性を確認しておく必要があります。
これらの確認が不十分なまま退去命令を進めると、従業員からの反発や法的リスクにつながる可能性があるため、事前準備は慎重に行いましょう。
2. 従業員への説明
退去命令の伝え方によっても、トラブル発生率は大きく変わります。入居者へ伝える際は、退職・異動・規程違反・社宅制度の廃止といった「退去を求める根拠」を明確に示し、退去期限や必要な手続きについて丁寧に説明することが大切です。
また、口頭のみの説明では誤解が生じやすいため、必ず書面で通知し、記録として残しておきましょう。
3. 各種退去手続きの実行
事前準備と従業員への説明が完了したら、実際の退去手続きを進めます。一般的な流れは次の通りです。
1. 退去申請の受理と社内承認
まずは従業員からの退去申請書類を受理し、退去希望日・転居先住所・緊急連絡先などの基本情報を確認します。そのうえで社内の承認フローを通し、正式な退去手続きとして扱える状態にします。承認の遅れは全体のスケジュールに影響するため、早めの処理が望まれます。
2. 貸主(オーナー)への解約通知(借り上げ社宅の場合)
借り上げ社宅では、企業がオーナーへ解約通知を行う必要があります。解約予告期間(一般的には1〜2か月ほど前)が契約書に定められているため、従業員の退去希望日から逆算して通知時期を調整しましょう。通知が遅れると余計な賃料負担が発生するため注意が必要です。
3. 引越し日程の調整・ライフライン解約の案内
従業員と引越し日程を調整し、退去日までに必要な手続きが完了するよう各種手配を進めます。また、電気・ガス・水道・インターネットといったライフラインの解約手続きについても案内しましょう。ガスの停止には立ち会いが必要な場合があるため、従業員に早めの予約を促すことが大切です。
4. 退去立ち会いと室内確認
退去当日は企業の社宅担当者または管理会社が立ち会い、室内の状態を確認します。壁紙の破損や設備の故障など、原状回復が必要な箇所を丁寧にチェックしましょう。必要に応じて写真や動画で記録を残しておくと、後日のトラブル防止に役立ちます。
5. 原状回復費用の精算・敷金の処理
原状回復が必要な場合は、社宅規程や契約書に記載された費用負担ルールに基づいて精算します。借り上げ社宅では、オーナーから提示された原状回復費用を企業が確認し、従業員負担分がある場合は社内で精算処理を行います。また、敷金がある場合は返還額の調整も必要です。
6. 社宅管理台帳の更新・鍵の返却
退去が完了したら鍵の返却を確認し、社宅管理台帳や従業員情報の更新を行います。社宅の空室状況や契約状況を正しく管理するため、最終的な記録の更新までが担当者の重要な業務です。
社宅の退去命令に関するよくあるトラブルと対応策

社宅の退去対応では、退去期限や原状回復費用の負担に関する認識違い、制度廃止への不満といったさまざまな問題が起こり得ます。ここでは、特に発生しやすいトラブルとその対策についてまとめました。
「退去期限が短すぎる」と不満が出るケース
退去期限に関するトラブルは非常に多く、「急に言われても準備が間に合わない」「転居先が見つからない」といった不満が従業員から寄せられることがあります。退去期限は入居者の生活に直結するため、理解を得られないまま進めると強い反発につながりやすい点に注意が必要です。
このケースにおける対応策としては、次の2点が挙げられます。
【対応策1】社宅規程に基づく退去期限であることを明確に説明する
退去期限は社宅規程に基づいて設定されていることを丁寧に説明し、合理的な根拠があることを理解してもらうことが大切です。そもそも規程が曖昧な場合はトラブルの原因になるため、事前の整備が欠かせません。
【対応策2】個別事情に応じて猶予を検討する
退職者の新居確保状況や家庭事情など、個別の事情を考慮して柔軟に猶予期間を設ける企業も多くあります。一定の配慮を示すことで従業員の不満を和らげ、スムーズな退去につながります。
「原状回復費用が高い」と揉めるケース
退去時の原状回復費用は、社宅トラブルのなかでも特に揉めやすい項目です。特に次のような場合にトラブルへ発展しやすくなります。
- 経年劣化と過失の区別が曖昧
- 入居時の状態記録が残っていない
- 見積もりの根拠が不明確
この状況における対応策としては以下が有効です。
【対応策1】経年劣化は会社負担、過失は従業員負担という原則を丁寧に説明する
国土交通省のガイドラインに沿って、「経年劣化は会社負担」「通常の使用を超える損耗や汚損は従業員負担」という原則を従業員にわかりやすく説明することが大切です。その際、入居時・退去時の室内写真を提示すると、客観的な基準に基づいて負担区分を示しやすくなり、説明の説得力も高まります。
【対応策2】見積書の根拠を明確に提示する
作業内容・単価・必要性などを具体的に示すことで、従業員の納得感が高まります。複数の見積もりを比較したうえで妥当性を確認していることを伝えると、費用の透明性が高まり、従業員も受け入れやすくなるでしょう。
社宅制度の廃止によってトラブルに発展するケース
社宅制度の廃止に伴う大量退去は企業側の都合で発生するため、従業員の不満が高まりやすい傾向があります。「急に制度をなくされた」「転居準備が間に合わない」といった声が上がりやすく、適切な対応を怠ると大きなトラブルに発展する可能性があります。
対応策としては次の3点がおすすめです。
【対応策1】早期の周知と説明会の実施
社宅制度の廃止については、できるだけ早い段階で周知することが欠かせません。可能であれば説明会を開催し、制度変更の理由や廃止までのスケジュールを丁寧に説明しましょう。質疑応答の時間を設けることで、従業員の不安や疑問をその場で解消でき、トラブル回避につながります。
【対応策2】十分な猶予期間を設ける
社宅制度の廃止を通知する際は、従業員が無理なく転居できるよう数か月単位の猶予期間を設けることが望まれます。特に繁忙期(3〜4月)や家族帯同者の場合は物件確保に時間がかかりやすいため、個別事情を踏まえた柔軟な対応が求められます。
【対応策3】代替措置の提示(住宅手当など)
社宅制度を廃止する場合、その代わりとなる支援策を提示することで従業員の負担感を和らげられます。たとえば住宅手当の新設・増額、引越し費用の一部補助、一定期間の家賃補助などが代表的です。企業として誠意ある対応を示すことで、従業員の納得感も高まりやすくなります。
社宅の退去処理を円滑に進めたい方には「社宅代行サービス」がおすすめ

社宅の退去対応には法的知識を要するほか、契約内容の精査やオーナーとの調整、原状回復の手配、書類処理など、複数の業務が同時並行で発生します。企業の社宅担当者にとっては負担が大きく、特に異動シーズンや退職者が重なる時期には対応が追いつかなくなるケースも珍しくありません。
こうした課題を解消し、退去処理を含む社宅管理全体をスムーズに進めたい企業に適しているのが 「社宅代行サービス」 です。専門会社が社宅管理業務を一括して担うことで、担当者の負担を大幅に軽減し、社宅運用の品質向上にもつながります。
社宅代行サービスを利用するメリット
社宅代行サービスとは、企業が自社で行っている社宅管理業務を外部の専門会社が代行する仕組みです。主に以下のようなメリットがあります。
- 担当者の業務負担を大幅に軽減できる :契約管理・更新手続き・退去調整といった煩雑な業務を外部に任せることで、社宅管理にかかる手間とリスクを大きく削減できます。
- 専門知識に基づく正確な対応が可能になる :法的知識や原状回復の基準、契約実務に精通したスタッフが対応するため、トラブル発生リスクを抑えられます。
- オーナーとの交渉や調整を任せられる :借り上げ社宅ではオーナーとのやり取りが多く発生しますが、代行会社が窓口となることでスムーズに進みます。
- 入退去の繁忙期でも安定した対応が可能 :社内リソースに左右されず、一定の品質で社宅管理を継続できます。
社宅代行サービスの特徴や選び方については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅代行サービスとは?メリット・デメリットや選び方を解説
実績豊富な社宅代行サービスをお探しなら
社宅管理を安心して任せられるパートナーを探している企業には、LIXILリアルティの社宅代行サービスがおすすめです。豊富な管理実績と全国ネットワークを活かし、社宅運用に必要な業務を一括でサポートしております。
退去処理においては、原状回復の調整や解約手続きの代行、退去立ち会いの手配、家主との交渉など、企業が負担を感じやすい業務を専門スタッフが丁寧に対応いたします。社宅管理の効率化やトラブル防止を図りたい企業様は、まずはぜひ一度ご相談ください。
まとめ
社宅の退去命令は、法的な判断や従業員への説明、オーナーとの調整など、多くの要素が絡む複雑な業務です。対応を誤るとトラブルにつながりやすいため、社宅規程や契約内容をしっかりと確認したうえで、段階的かつ慎重に対応を進めていきましょう。
一方で、社宅管理を自社だけで完結させるのは負担が大きく、繁忙期には対応が追いつかないこともあります。こうした課題を解消し、社宅運用を安定させたい企業には「社宅代行サービス」の活用が有効です。
ぜひ社宅代行サービスの導入によって社宅管理の効率化とトラブル防止を両立し、従業員にとっても企業にとっても安心できる運用を実現していきましょう。